しいたけ.推薦、マキャヴェッリ著「君主論」は運命に立ち向かう者への讃歌だ。

皆さんは「しいたけ.」という方をご存知だろうか?
“占い師”というと聞こえは悪いかもしれないが、
私個人について言えば、普段占いなどは信じない・・・正確に言えば“自分に都合が良いところだけ参考にする”スタイルだが、このしいたけ.氏の占いはそれぞれの星座の人物評のような面があり、それが非常を的を射ており、かなり興味深い。
そのしいたけ.氏が、ある雑誌の記事の中で古典的名著について触れていることがあった。その名著とは他でもない。
ニコロ・マキャヴェッリ著「君主論」である。
しいたけ.氏は次のように述べた上で、お勧めする一冊に取り上げている。
運について考えるようになったきっかけは、大学生の時に歴史哲学の授業でマキャヴェリの『君主論』を学んだことです。
そこでは時代の権力を持つ人は「力量、運、時代性」の三つが必要だと言われている。どんなに実力があっても、運に恵まれない場所にいたらどうしようもない、と。
AERA2019年9月12日号
この本は16世紀に書かれた有名な古典的名著。
当時の動乱期のヨーロッパにおいて、“いかにしてイタリアという国家が生き抜いていくか”という政治政策が具体的に細かく書かれている。必然的に国家論、組織論、リーダー論的な観点からの主張が多く、現在でもビジネス書のような視点から読み解かれることが多い。
しいたけ.氏のように“運”という観点から読み解くのは珍しい。
けれども、その観点から改めて本書を読み返すと、よくあるリーダー論、組織論とは違う別の「君主論」の姿が見えてくることに気づく。“君主”のあるべき姿を問いながらも、運命という巨大な波に人間がどのように立ち向かっていくべきかという人生論がこの本には隠されているのだ。
君主論で重要な2つの概念
先程のコメントの中で、しいたけ.氏は君主論の中で「力量、運、時代性」が重要だと書かれていると述べているが、マキャヴェッリが重要視したのは
「力量 (イタリア語で”ヴィルトゥ”)」
「運命 (イタリア語で”フォルトゥナ”)」
の2つだ。
力量 (ヴィルトゥ) はもともとラテン語で「男性、雄々しさ」を意味する”ヴィルトゥス”から来た言葉で、マキャヴェッリは特に剛毅さや機敏な知恵という、まさしく日本語の”力量”のニュアンスに近い意味で使っている。一方の運命(フォルトゥナ)は古代ギリシャでは”ファトゥス”と呼ばれ、運命の糸を分かち、紬、絶つ、三人の女神にたとえられていた。運命の不確実な性質を女性のきまぐれな姿に見たのだ。
そのような気まぐれな運命 (フォルトゥナ) を引き寄せるためには、雄々しく、知恵のある手腕を意味する「力量 (ヴィルトゥ)」を持っていなければならない。
だから権力を握るものには「力量と運命」が必要であるとマキャヴェッリは説いたのだ。
しいたけ.氏が挙げた「時代性」というのは、この「運命」を補足するような形で使われており、「必要性、時機、好機」という意味で使われる。たとえば「必要性に応じて、柔軟な政策を出せる力量が重要だ」と言ったような使われ方である。
この「君主論」の中ではこの2つの概念が最重要であり、これが理解できているとかなり読みやすくなる。そして、それが理解できていればこの本の中核の考え方がわかる。それは
「何か事を成し遂げようとするなら、移ろいやすい運命を引き寄せる力量を磨くことが重要である。その上で、今この瞬間にいかなる力量を発揮すべきかを見極める冷静な判断力を備えておかなければならない。」
ということである。
「君主論」をいわゆる”ビジネス的”な意味で役立てようとするのなら、これさえ理解できていれば十分だ。あとはそれを現実にどう応用していくかだけの話になる。実際「君主論」を自己啓発書、組織論として解釈するビジネス書では、ほとんどこれだけしか書かれていない。
だが、これでは君主論の魅力の半分も理解できていない。
これほどの名著でありながら本当にもったいないと思う。
君主論の面白さはここまで理解した上でさらにもう一段深く読みとくことで、はじめて理解できるものなのだ。
そこで本書の内容をさらに深堀りし、マキャヴェッリが本当に伝えたかったことを探るために、この本の概略を少し説明させて欲しい。
イメージの悪さは天下一品
昔から名著として評判の高い書だが、“マキャヴェリズム”という言葉のダーティな印象から一般にはとっつきにくいイメージを持たれることが多い。
というのは、“マキャヴェリズム”という言葉自体が「目的のためには手段を選ばない冷酷非道さも必要である」というイメージとして広く流布しているからだ。
実際、この君主論には
「国を維持していくためには、冷酷非道な手段や、人を裏切ったり欺いたりする行為もあってしかるべき」
といった表現や
「人間というものは狡猾で嘘つきで信用ならない生き物である」
とした上で君主がどうあるべきかを説いている箇所が散見される。
本書の構成自体も大部分がそのような冷徹な国家運営の方法について割かれている上に、それらの説明が非常に淡々と繰り広げられ、読者を引きつけるようなドラマチックな部分がほとんどない。
だが、実はその「面白くなさ」にもれっきとした理由がある。
マキャヴェッリがこの本を書いた理由
この君主論が政治哲学の書としてあまりにも有名なため、マキャヴェッリも政治学者あるいは哲学者だったのだと誤解されることが多い。だが、実は彼はイタリアはフィレンツェの外交官だった。しかもどちらかと言えば、上級官僚から使いっぱしりにされるような低い身分だ。
当然彼自身に国をどうこうするような権力はない。
ではなぜマキャヴェッリはこの本を書いたのだろうか?
先程マキャヴェッリは外交官だったと書いたが、この「君主論」を書いた時には自分が就いていた政権が倒れてしまったために、外交官をクビになっていた。それだけではない。一民間人として生活をしていたところ、とある政治事件に関わっていたとして無実の罪で投獄。拷問を受けた後に釈放されたものの、その後は酒と博打に明け暮れる日々だったようだ。
その生活を何とか挽回しようと、次期君主と目されていたメディチ家のロレンツォ二世に自分を雇ってもらおうと必死に書き上げた論文。それがこの「君主論」だった。
いわばイタリアの国家統一への道筋を理詰めで説明した上、「このようにすればあなたは立派な君主になる。ついては、それを補佐するためにぜひ私を雇って欲しい。」という自身を売り込むのがこの本の目的だった。今で言えば”就職活動”のようなものだろう(残念ながらこの論文はロレンツォ二世の目に触れることはなく、外交官への道は断念せざるを得なかったのだが・・)。
では、なぜマキャヴェッリがそこまでして外交官に返り咲こうとしたのだろうか。
この点を掘り下げることで「君主論」でマキャヴェッリが伝えたかった熱い思いが浮かび上がってくる。
悲劇の医者イグナーツ・センメルヴェイス
それを探るのに、ひとつ参考になる事例を紹介しておきたい。19世紀のオーストリアに存在した、イグナーツ・センメルヴェイスという若い医者の話だ。
当時の病院で妊婦が出産する際に、分娩を助産婦が行うよりも医者が行った方が妊婦の死亡率が高いという現象が発生していた (助産婦が3%に対して医者は30%)。
その様子を見ていた研修医のセンメルヴェイスは、ある仮説を立てた。
その仮説とは「医者の手から何かの物質が発生しており、それが原因で妊婦が死亡しているのではないか」というものだった。これだけ聞くと奇妙な仮説だが、実際にその仮説の下に分娩の際に消毒液による手洗いをするようにしたところ、死亡率が激減したのだった。
実は医者の手に付着していた細菌が原因だったのだが、当時はまだ細菌という概念自体がなかったため、このセンメルヴェイスの仮説は医学界にまったく受け入れられなかった。それどころか、センメルヴェイスは「奇妙な仮説によって、医者を貶めようとした」としてなんと病院から追放されてしまう。
もしセンメルヴェイスの説が正しければ、医者は自分たちの責任で膨大な人数の妊婦を死に至らしめたことになる。当時は細菌という概念すらなかったのだから仕方のないことだが、医者の立場としては「知らなかった。ごめんなさい。」で済まされる話ではない。
その上、その説を主張しているのは若手の研修医でしかない。「この若造が!適当にデタラメを言ってるんじゃないぞ!」というわけだ。
それでも自説を曲げようとしなかったセンメルヴェイスは、そのことを告発する書籍を出版しようとしたのだが、強制的に精神病院へ収監。そこから逃走しようとした時に負った傷がもとで、その後死亡してしまったのだった。
今ではセンメルヴェイスが正しかったことは科学的に立証されているのだが、当時は誰もその新事実を信じなかった。いや、信じたら自分が築いてきたものがすべて崩壊してしまうという恐怖から、その事実を信じたくなかったのだ。
ちなみに、現在では、このような「通説と合致しない新事実を拒絶する傾向」のことを「センメルヴェイス反射」というようになり、世間で知られるようになっている。
センメルヴェイスは時代を読めない愚者だったのか?
話を「君主論」に戻そう。
先程も書いたようにマキャヴェッリは「君主論」において
「何か事を成し遂げようとするなら、移ろいやすい運命を引き寄せる力量を磨くことが重要である。その上で、今この瞬間にいかなる力量を発揮すべきかを見極める冷静な判断力を備えておかなければならない。」
という主旨のことを述べている。
この言葉を字義通りに解釈するのなら、センメルヴェイスは運命を引き寄せる力量がないにも関わらず、無謀な戦いを挑んだ愚か者だったということになるのだろうか?
たしかに確実を期すのであれば、仮に同じ主張をするにしても、せめて自分のキャリアを磨いて研修医を脱するべきだったのかもしれないし、自分の説をしっかりと理解してくれる上司が現れるのを待つべきだったのかもしれない。あるいはその「医者から発せられている物質」が何なのかをじっくりと研究するべきだったのかもしれない。
だが、彼はそんな時局も考慮せずに自らの説を堂々と報告し、それが医学界に受け入れられなければ一般の人に訴えるべく本の出版さえ企画した。実際、彼の説は”科学的には”正しかったのだ。それにも関わらず彼は惨憺たる扱いを受け、命を落とすことになった。
彼は人生の選択を誤ったのだろうか。時代を読めない愚か者だったのだろうか?
私は違うと思う。
運命に抗う意思
確かに彼はもっと良いタイミングを見計らうこともできたかもしれない。だが、それはより多くの妊婦が命を落とすことになることを黙って見過ごすことになる。それは彼の信念にとって受け入れられないことだったに違いない。
なるほど、”成功者かどうか”という意味ではセンメルヴェイスはたしかに失敗した側の人間だったかもしれない。時代性を読み間違えた上、運命を引き寄せる力量もなかった。
挙げ句の果てには、自説にこだわったことで命を落とす羽目になった。あえて勝ち組か負け組かを選別するのなら、彼は後者に属するのだろう。
だが、彼は自らの行動を後悔しただろうか。
否。「なぜ理解してもらえないのか」という忸怩たる思いはあっただろうが、その行動に迷いはなかったはずだ。センメルヴェイスはたとえ周りからどのような目で見られようと、自らが正しいと信じた道を進み、自らに課せられた使命をまっとうした。そこに後悔の念は一片たりともなかったのではないだろうか。
私は「君主論」を書き上げたマキャヴェッリも同じ心持ちだったのではないかと思う。
センメルヴェイスは目の前の患者たちを死なせたくないという意思から、自らの説を広く訴えかけた。
マキャヴェッリは自らの愛したイタリアという国を守りたいという意思から、自らの説を次期君主に訴えかけた。
彼ら二人には共通している点がある。
それはたとえ運命がどうであろうと、自らの信念を貫こうとする強い意思を持っていたことだ。
マキャヴェッリの抱えた矛盾
マキャヴェッリは確かに力量 (ヴィルトゥ) を磨き、運命の女神 (フォルトゥナ) が微笑んだ時に果敢に突き進むべく、常に冷静に、冷徹に事に臨むべきだと説く。だが、それと矛盾するかのように彼はこの書の終盤において次のようにも述べる。
「もともとこの世のことは、運命と神の支配に任されているのであって、たとえ人間がどんなに思慮を働かせても、この世の進路をなおすことはできない。いや、対策さえも立てようがない。(中略)しかしながら・・・仮に運命が人間活動の半分を、思いのままに裁定しえたとしても、少なくともあとの半分か、半分近くは、運命がわれわれの支配に任せてくれていると見るのが本当だと、私は考えている。」
今までの自分の主張をすべてちゃぶ台返しするかのような物言いである。
ここに至るまでマキャヴェッリは”運命には逆らえないのだから、運命が微笑んだ時に歩を進めるべきだ”と述べてきた。それにも関わらず唐突に、何の根拠も示さずに”運命の半分はわれわれの手の内にある”かのように語りだすのだ。
さらにマキャヴェッリは
「運命は変化するものである・・・人は慎重であるよりは、むしろ果断に進む方が良い。」と続け、「運命を力づくで征服せよ」とまで述べるのである。
矛盾している。少なくともこの終盤の物言いは、それまでの言説と整合性がとれていないと言って差し支えないだろう。
だが、それがいい。
人間とはそもそも矛盾した生き物なのだ。
誰かを愛していると同時に憎くらしく思う時もあれば、辛く苦しい時にこそ生きる喜びを感じる時もある。秩序と無秩序。冷静さと情熱。そのような矛盾を人は常に抱え、それらに折り合いをつけながら必死に生きている。だからこそ人生は輝くのであり、矛盾のない整然とした平坦な人生を歩いても生きる喜びなど感じることはできない。マキャヴェッリの「君主論」もまたそういった矛盾点にこそ彼の本心が現れているとみるべきだと思う。
運命に抗う人への讃歌
たしかにこの「君主論」において、マキャヴェッリは努めて冷静に持論を展開している。しかし、丁寧に読むと序盤から彼のふつふつと沸き起こる情熱の炎が湧き出しているのが端々に見てとれる。私には序盤から冷静に抑え込んできた、たぎるマグマのような思いが終盤において、遂に爆発したように感じられてならない。
すなわち
「運命 (フォルトゥナ) は変えられる。強い意思 (ヴィルトゥ) を持って立ち向かい、運命を征服するのだ!皆のものよ、恐れず前に進め!」
という信念だ。
マキャヴェッリは彼自身運命と時代に翻弄された人生を送り、はかなくも短い人生を遂げた。彼がこの本で伝えたかったこととは、運命 (フォルトゥナ) の持つ圧倒的な力の前に足をすくませる人々に、一歩を踏み出させる勇気を与えることではなかったか (この勇気もまた「力量 (ヴィルトゥ)」のひとつだろう)。
なるほど、マキャヴェッリの言葉はたしかに苛烈である。
宗教改革という嵐が吹きすさび、国家と国家が容赦なくぶつかり合う時代の到来を予兆するような混迷の中で書かれたのだから無理もないだろう。だが、その言葉の苛烈さや冷徹さという”形”に目を囚われては、マキャヴェッリの真のメッセージを受け取ることはできない。
文庫本であれば150ページほどで決して大著とは言えないが、その端々からほとばしるマキャヴェッリの情熱は古典的名著と呼ぶに恥じない圧倒的パワーを秘めていると思う。もしあなたが自分のちからではどうしようもない運命(フォルトゥナ) の前に膝を屈しようとしているのであれば、ぜひ一度この本を手にとって欲しい。運命に立ち向かう勇気と具体的な方法を得る大きなヒントになるはずだ。
という訳で、今回ご紹介したのはこちら。ニコロ・マキャヴェッリ「君主論」でした。今回も長文を最後までお読み頂きありがとうございましたm(_ _)m
崩壊する文明の運命に立ち向かった男。ル・ボン「群衆心理」

社会心理学の歴史的名著、ギュスターヴ・ル・ボン著「群衆心理」。
この本をご存知だろうか。
この本は著者のル・ボンがフランス革命の混乱の後に書いたもの。革命の最中、民衆が”群衆”と化し、社会に破壊と殺戮の嵐を招いた激動の様子を観察し、その群衆がなぜそのような行動を取ったのかを社会心理学的な観点から分析したものだ。
当時は群衆を研究対象とした本はほとんどないどころか、そもそも"群衆"に特別な意味を待たされていなかったため、群衆を真正面から取り扱ったこの本は、社会心理学研究の発展への道を開いた名著と言われる。
だが、その過激な内容と、著者ル・ボンの激烈な毒舌のために社会心理学の中でも異端扱いをされている。その故、名著と言われながらも、社会心理学の世界においては評価が著しく低いようだ。
確かに本を正しく評価することは難しい。
そもそも著者の意見が正しく理解されないこともある。
あるいは著者が伝えたいことは全く無視された上で、著者の意図とは全く違うように捻じ曲げられて、散々な評価を受けているものも多い。
その意味でこのル・ボンの「群衆心理」は”もっとも不当に評価されている”古典的名著の一つといえるだろう。
しかし、私は今こそこの本の真の価値が見直されるべき時ではないかと思う。
なぜなら、この書は単なる社会心理学的なものではなく、人類の文明社会がいかに衰退し、崩壊していくのか、そのダイナミックな歴史転換のシステムを描いたものだからだ。
現代は数百年、あるいは千年に一度の大変革の時代だと言われる。その変革の時代にこそ、このような”異端の書”に改めて注目する意義があるのではないだろうか。
群衆心理の内容
この「群衆心理」についてのよくある内容解説は、大体次のようなものだ。
「人間が大勢集まって群れをなすー群衆化するーと、個人の時には現れなかった特別な心性や行動様式を示す。そこでは、動物の群れにおけるのと同様、盲目的な付和雷同性が支配的となり、理性的な判断はできなくなったしまう。
このような「群衆」は巧みな言葉やスローガンを用いる指導者に扇動され、多くの場合、過激な破壊行動を行い、しばしば犯罪をも平気で犯す。
実際、フランス革命においては、ロベスピエールのようなリーダーに唆された盲目的な群衆が猛威を揮ったとして断罪された。
このような心理が発動する原因は、人々が群衆化すると自分で考える力をなくし、単純なイメージに影響を受けやすいことにある。」
この内容の説明自体は間違っていないと思う。
だが、これを眺めただけでル・ボンの伝えたいことを理解し、十分に評価できるのかと言えばかなり疑わしい。
ル・ボンをこき下ろした歴史学者
ル・ボンが示したような群衆的な心理分析については、現在ではかなり市民権を得ている。特に今年2021年初頭、アメリカ大統領選挙において選挙システムに不審を抱いた群衆が連邦議会に大挙して押し寄せた事件を観て、”群衆化した民衆の恐ろしさ”を記憶している人も多いだろう。
ただ、このル・ボンの「群衆心理」という書自体は、昔からかなり不当な評価を受けていたようだ。
例えばこのル・ボンの著作を批判した人物にジョルジュ・ルフェーブルという歴史学者がいる。
ルフェーブルはル・ボンの功績として、彼が今では常識とも言えるほど流通している「群衆」という概念を、社会の動きを解釈する上での概念のひとつとして世界で初めて取り上げたことを挙げている。
だが、ルフェーブルは「彼の功績は、それ以上のものでは決してない」とした上で、
- ル・ボンは群衆の心理と個人の心理を混同している (およそ社会心理学の研究としては成立していない)
- ル・ボンは動物の群れと同じように人間の群衆の中でも心理状態が病的に感染すると言う。しかし、人間の群衆において特定の心理が伝播するのは事実だが、動物の群れのシステムとは全く違う。
- 群衆の心理について語っているくせに、それを真剣に研究する気はさらさらなかった
と述べ散々にこき下ろしている (ジョルジュ・ルフェーブル著「革命的群衆」)。
ルフェーブルのような観点からル・ボンの主張を批判する言説は多い。
そのようなル・ボンの群衆心理への評価は果たして正当なものなのだろうか。
残念ながら、これらの批判は的外れと言わざるを得ない。むしろルフェーブルのような言説こそル・ボンが社会を混乱へと導く要因の一つと考えたものであり、彼が孤軍奮闘した相手であったのだ。
ルフェーブルの社会心理学の研究における功績について述べる素養は残念ながら私は持ち合わせていない。しかし、ことル・ボンへの批判に関しては、ルフェーブルの社会心理学的な専門性ゆえに、群衆が帯びる社会的心理というレンズの向こうにル・ボンが見通した近代主義への批判的思想を看取することが出来なかったようだ。
ル・ボンが見通した文明の未来
群衆心理というタイトルの通り、ル・ボンは人が集団になった時に表れる熱に浮かされたような破壊的行動をこの本の中で分析し、その直接的・間接的原因を種族、慣習、制度、教育などの文化人類学的な側面から読み解いている。
だが、彼が「群衆の心理」は群衆の動態が引き起こすであろう未来への危惧を示すための、ひとつの手段に過ぎなかった。重要なことは彼がどのような危惧を感じ取ったのかであり、その危惧を表明するための手段が学問的に正確でないことをあげつらうことは無意味である。むしろそれによって、ル・ボンの危惧した未来像が世間に共有されることを妨げたという意味では、致命的な損失を招いたとさえ言えるかもしれない。
では、ル・ボンが危惧した未来とは何だったのだろうか?
それはズバリ「文明の崩壊」である。
ル・ボンは群衆の時代、群衆によって世界が翻弄されることで、文明社会、中でもヨーロッパ的な西洋文明が崩壊する未来を予見したのである。それは彼自身の次の言葉に明確に表されている。
群衆の台頭こそは、恐らく西欧文明の最終段階を画し、新社会の出現に先立つあの雑然とした混乱期への復帰を示すものであろう。(中略)群衆は、もっぱら破壊的な力をもって、あたかも衰弱した肉体や死骸の分解を早めるあのバイ菌のように作用する。文明の屋台骨が蝕まれるとき、群衆がそれを倒してしまう。群衆の役割が現れてくるのは、その時である。
よくある本著「群衆心理」の評では、「扇動的な指導者に群衆が付和雷同的に動かされて社会を破壊する。その群衆心理のシステムをこの本は分析した。」と言われる。それは半分正解だが、半分は不正解である。
上記の言葉のように、ル・ボンによれば、まず衰退する文明の姿が徐々に現れ、それに呼応する形で人々が群集心理的な(破壊的な)活動を示し、ついには文明を破壊するに至るのである。その逆ではない。
この違いは決定的である。
なぜなら、人々が群衆化することで文明が崩壊するのであれば、人々が群衆化しないようなシステムを構築することで、それを防ぐことができる。だが、ル・ボンが述べるように文明の衰退と崩壊が先に始まり、群衆がそれを加速するだけの存在なのであれば、たとえ群衆心理の暴走を防ぐことに成功しても文明の崩壊を回避することはできないからだ。
シュペングラーの文明史観
では、なぜル・ボンのいうように「文明の衰退と崩壊」がまず最初に起こるのだろうか。
一般的な理解では文明とは特定の種族、民族の繁栄を示す、まさに人類の最骨頂とも言えるものだ。
だが、ル・ボンは文明をそのように解釈していない。まるで放物線の頂点・・・上へと上昇する運動エネルギーが下降への動きに変化するターニングポイントのような場所にあるもの、それが文明だと解釈しているようだ。
これは20世紀初頭の思想家・オズワルド・シュペングラーが表した「西洋の没落」において描かれる、文化の興亡を周期的に循環するシステムだと解釈する考え方と近い。
「西洋の没落」においてシュペングラーが示した世界観は、西洋文化に限らず、文化というものはすべからく没落する運命にあると考えるものだ。文化には大なり小なり栄枯盛衰のパターンがあり、幼年期>青年期>壮年期>老年期という具合に人の人生のように流れていく。
シュペングラーはそれを春夏秋冬の季節の流れになぞらえて
春 : 勃興
夏 : 成長
秋 : 成熟
冬 : 衰退
という運命をたどるとし、西洋文化は18〜19世紀には秋 (成熟) になり、20世紀初頭には冬 (衰退) の段階に入ったと分析。秋から冬に向かう転換点の前後を文明の全盛期と捉えている。
ここで注意すべきは、文化と文明の違いだ。
文化と文明の違い
シュペングラーによれば「文化の人間はその力を内部に向け、文明の人間は外部に向ける」という。
少し噛み砕いて説明すると、文化という段階において人間が持つさまざまな力 (活力、知力)は、英語のCulture (文化) の語源が示すように、自らを掘り下げる (cultivate) ことによって、さまざまな知恵や芸術を作り出していく。
それが文明の時代になると、その力は外部へと拡張するように変化し、自らを掘り下げて新しい物を創り出すことが困難になるのだ。
シュペングラーは一大文明として栄華を極めた帝政時代のローマ文明を挙げ
「ローマ文明は、見かけだけの青春の力と充実でもって、隆々とそびえ立ち、そうして若いアラビア文化から光と空気とを取ったのである。これが歴史におけるすべての没落の意味である」
と述べた。
すなわち文化の段階に存在した自らの中からほとばしり出る栄養が尽きると、外部の世界へと拡張し、そこから栄養を吸い付くし自らの力へと変換しようとする文明の段階へと至る。この段階に至れば、外部からの栄養を吸い尽くした段階でその文化は衰退し、崩壊してしまう運命を避けられないということである。
しかしながら、この文化から文明という外部拡張の時代への変化もまた避けられない。なぜなら文化の高度化はその民族や国家に経済的繁栄もしくは芸術的繁栄、もしくはその両方を実現するため、必ず膨大な人的、経済的エネルギーを必要とする。
だが、どれほど優れた文化であっても無尽蔵にそのエネルギーを生成できるわけではないため、それを外部への拡張によって補わんとするのは必然なのである。
シュペングラーの歴史観によれば、このようにして民族の文化は衰退へと向かい、その衰退期を経てまた新たな興隆の周期へと移り変わっていく。
ル・ボンの歴史観
群衆心理のル・ボンの言説を読むと、彼もこのシュペングラーの歴史観に近い感覚を持っていたようだ。そのル・ボンにとってフランス革命とその後の混乱は、まさに西洋文化がその頂点を過ぎ衰退する文明期に入っていることを予感させるものだったに違いない。
実際、ル・ボンは本書の最後はその運命を回避することはできないと結論付けている。
一つの夢を追求しながら、野蛮状態から文明状態へ進み、ついで、この夢が効力を失うやいなや、衰えて死滅する。これが、民族の生活が周期的にたどる過程なのである。
この場合の夢とは民族の中で共有される宗教や哲学のような観念と思ってもらえば良いだろう。ル・ボンはこのような夢が共有されることで民族は繋がりを強く持ち、文化が発展していく原動力となると本書の中でも解説している。その夢が効力を失ってしまえば、文明は再びそれ以前の野蛮状態へと回帰する運命にある。それがこの結論の意味であろう。
まさにル・ボンが生きた時代はそのような転換点であり、将来においては西洋文明が衰退の一途をたどることは必然である・・・その絶望の未来を直視し、それを避けられぬ要因を説いたのがこの著「群衆心理」だったのだ。
「群衆心理」から学ぶべきこと
では、この著書によってル・ボンは我々に何を残してくれたのだろうか?我々はル・ボンから何を学ぶべきなのだろうか?
多くの人はこの書を解説する際によくある結論はこうだ。
「他人の意見に安易に扇動されないように、一つ一つの物事をイメージではなく、しっかり自分の頭で考えることが大事。それによって群衆化することを防ぐことができる。特にSNSで偏った情報が大量に拡散しやすい現代では必読の書である。」と。
確かにこの著作にはいかにして集団は群衆化するのか、群衆化した時にどのような行動を示すのかが具体的に書かれている。したがって、”ハウツー本”的な読み方をすればそのような結論も引き出せるだろう。
だが、それではこの書の真の迫力は伝えきれていないのではないかと思う。
私が思うに、この書の最大のメッセージは「世の中には取り返しのつかないこと、後戻りできないことがあることを知れ。」ということではないだろうか。
繰り返しになるが、ル・ボンがこの書を著したきっかけはフランス革命によるヨーロッパ世界の大混乱であった。ル・ボンはフランス革命についてこう述べている。
「純理の示すところに従っては、社会を徹底的に改造できないということを発見するために、二十年間に数百万の人間を殺戮し、ヨーロッパ全土を混乱に陥れなければならなかった。」
日本ではフランス革命と言えば、絶対王政による圧政を志のある民衆が打ち砕き、民主主義国家の基礎を打ち立てた”素晴らしい民主革命”だと考えられている。しかし、これは全くのデタラメである。
フランス革命とは、たった数十年しか生きていない一部の人間が、それまでの歴史で少しずつ紡がれてきた社会の秩序をすべて破壊し、数学の計算のように頭の中で作られた人工的なルールに基いて、社会を一から作り直そうとする暴動だった。
当然そんな凶行がうまく行くはずもなく、数十年間の間に膨大な死者と社会混乱を招いた挙げ句、軍事独裁政権の誕生とヨーロッパ全土を巻き込んだ大戦争を引き起こした。
まさにル・ボンの言う通り「理性の力で社会を改造することなどできない」という当たり前の事実を再確認するために、ヨーロッパ世界はとてつもないツケを払うことになったのだった。
現代においてもそのような「理性による社会変革」という幻想は根強い。
何か大きな社会問題が起こるたびに、「今までのやり方では駄目だ」「革新的な解決策を」「どこかで美味い汁を吸っている奴らの既得権益をぶち壊せ」などとドラスティックな変革を求める声が必ず上がる。実際バブル崩壊後の日本はそのようにして、それまでの日本社会で培われてきた慣習や制度をことごとく破壊して来た。
その結果、一億総中流と言われた社会の構造は変化し富の二極化が進行。世界第二位と言われた経済力も今では風前の灯火。その間に、隣国中国との軍事力の差も圧倒的に開いてしまい、逆に東アジアの不安定化を促進してしまった。
米中新冷戦と言われる中で「日本はどのようにするべきか?」などと言っているが、もはや日本にできることなど何もない。数十年後、中国の自治区になるか、アメリカの植民地になるか、どちらの道を選択するかしか道は残されていない。
もうどうしようもない。
日本の失われた30年は二度と取り返しがつかない。
これが現実だ。
まさにル・ボンがこの書の最後で書いた通り”一つの夢を追求しながら、野蛮状態から文明状態へ進み、ついで、この夢が効力を失うやいなや、衰えて死滅する。”
これが今後日本が歩む道のうち、最も可能性の高いシナリオなのだ。
だが、最後に付け加えるとすれば、それは”だから諦めろ”という話ではないということだ。
世の中にはどうしようもないこと、取り返しのつかないことがある。
しかし、それを知っていれば今の行動を変えることはできる。確かに状況に合わせて変化していくこと、新しいものを吸収していくことは重要だ。だがそれは物事を根本的に作り直すこととイコールではない。今までの歴史的な叡智を残し、活用し、必要な部分だけを少しずつ調整しながら進んでいく。遠回りのようでいて、実はそれがもっとも近道であるということもあり得るのではないだろうか。
そのような選択肢を考えることができる歴史的叡智が宿っていること。それこそが世界最古の国である日本が持つ、もっとも強力な武器なのではないだろうか。
最後に、その諦めない力の重要性を強調するため、16世紀の政治思想家ニコロ・マキャヴェリの次の言葉を引用して、今回の投稿を終えたい。
歴史全体を通じてみても、私は次のことのまごうかたなき正しさを、ここで改めて断言してはばからない。つまり、人間は運命のままに任せていくことできても、これには逆らえない。また、人間は運命の糸を織りなしていくことはできても、これを引きちぎることはできないのだ。
けれども、何も諦めることはない。なぜなら、運命が何を企んでいるわからないし、どこをどう通り抜けてきて、どこに顔を出すものか、皆目検討もつきかねる以上、いつどんな幸福がどんなところから飛び込んでくるかという希望を持ち続けて、どんな運命に見舞われても、またどんな苦境に追い込まれても投げやりになってはならないのである。
今回も長文を最後までお読み頂き有難うございました😆
読書に成果なんか求めなくていい。著者との対話こそ真の醍醐味だ。
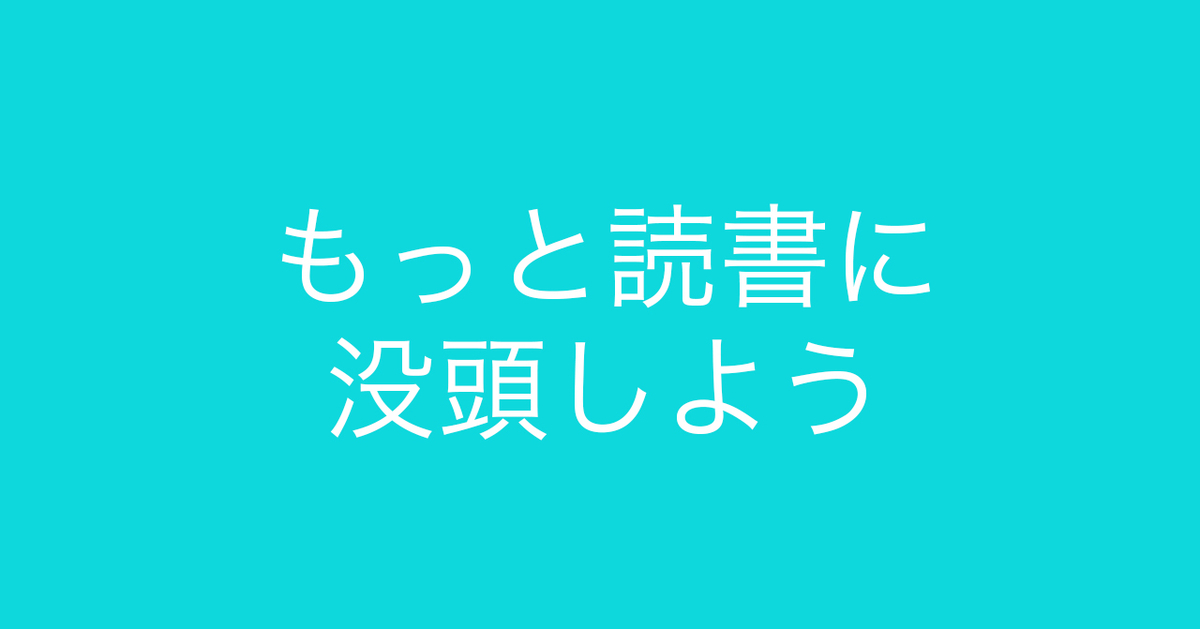
古今東西、読書には様々な方法がある。
その中でも最近特に言われるのが「本を読んだら、速やかにアウトプットすべし!」という方法だ。
一昔前なら読書日記をつけることが関の山だったのだが、そこはネット全盛の現代。
ブログやSNSなどで誰でも手軽に発信できるようになった今では、自分以外の誰かに本の内容を伝えることで、”より効率的に”、”より体系立った知識として”、本の内容を習得できるというわけだ。
そのようなアウトプットを目的とした場合、本を読む時の姿勢も変わってくる。
アウトプットをする以上は誰かからの反応を得たいのが人間の性であるから、当然本を開く時からアウトプットするためのネタ探し的な姿勢になる。さらには、本の探すときにすらそのような目的意識から本を選ぶようになるだろう。
なるほど、読書をする目的は人それぞれだ。
試験勉強のためにする読書もあれば、ビジネス上のスキルを磨くために必要な読書もある。その種の目的のためには読書に効率と成果の最大化を求めるのはやむを得ないかもしれない。
だが、そのような目的の読書であったとしても、それが貴重な人生の時間を費やすのであれば「仕事のために読むのだから、仕事が終われば一切合切捨て去ってしまって構わない」ということにはならないはずだ。たとえ短期の目標であったとしても、少しは人生の役に立つことを願うだろう。
そうであれば、短期的な効率や成果を求めるだけに留まらず、自らの人生を豊かにするための手段として読書の意味を考え直すことも必要ではないだろうか。
前置きがいささか長くなってしまったが、今回は「読書に効率や成果など求める必要はない」という立場から正しい読書の方法について考えてみたい。本を読んで成果を出すことに疲れた人たちにもう一度読書の魅力を噛み締めてもらえたら幸いだ。
知識に対する根本的な錯覚
まずもってはっきりさせておきたいことは「読書の目的は、知識や教養を身につけることではない」ということだ。
恐らく多くの人が本を読む目的として
・知識を得ること
・教養を身につけること
を挙げるだろう。
私は知識と教養は別物だと考えているが、今回の本筋からは外れるため便宜上これらを「知見を広げる」という目的だとまとめて話を進めることにする。
※教養と知識の違いについては以前の投稿にも掲載したので、よろしければこちらも。
多くの人々は知識を得る、あるいは知見を広げるということに関して根本的に誤解をしていると思う。
人々は新しい何かを知ることで、今までにできなかったことができるようになったり、自分の能力が向上したり、または自分の知らなかった世界が開けてくると考えているようだ。
確かに知見を広げることによって、そういう”今までの自分になかった力”を身につけることができるという側面はある。しかし、それは知見を広げることの役割を半分しか理解できていないと思う。
新しい何かを身につけたと言っても、それが世界の誰も知らない、誰も理解できないような全く新しい心理を発見であるケースはまずあり得ない。ほとんどの場合が、現在の誰かや過去の偉人が発見した物事を再発見したということに過ぎない。
つまり新しい知見を知り得たと思った時には同時に、過去の偉人が持ったより高い視座や広い知見が存在し、自分は後追いでそこに追いついたに過ぎないことを肌身で感じるはずなのである。
読書に伴う責務
かつて中世の人文主義者ソールズベリーのジョンは、12世紀の思想家ベルナールの言葉を引いて次のように語った。
「ベルナールスはわれわれをよく巨人の肩の上に乗っている矮人(わいじん)に準えたものであった。われわれは彼らよりも、より多く、より遠くまで見ることができる。しかし、それはわれわれの視力が鋭いからでもなく、あるいは、われわれの背丈が高いからでもなく、われわれが巨人の身体で上に高く持ち上げられているからだ、とベルナールは指摘していた。私もまったくその通りだと思う。」
現代の私達がさまざまな知見を得ることができるのは私達の能力のおかげではない。ここに至るまでの過去の偉人たちの功績があったればこそなのだ。
私達がいま享受している物のほとんどすべては、過去の偉人たちの蓄積の元に達成された果実だ。そうであるならば、私達が新たな知見を得た時には同時に、それを発展させ、それを知らぬ人々に伝えていく義務、さらに次の世代に受け継いでいくために努力する責任が生まれるはずなのだ。
当然そのような責任は本を読む側にだけ帰せられるべきではない。
書き手にも同様の責任が伴う。
本を読む人、本を書く人、その両方が知識や知見を広げ、人々へ受け継いでいくという責任を実感しながら本に関わるべきである。
もちろん、その責任の果たし方の中に「アウトプットする」という行為が含まれることもあるだろう。私も「アウトプットをするな」と言うつもりはない。だが、それは手段の一つであって目的ではない。ましてや、それに囚われて本を読むことへの正しい向き合い方を忘れるのは本末転倒だろう。
では本を読む目的とは何だろうか?
古くから読書には様々な意味が見出されてきたが、その中でも重要なものは人生の指針を導き出すことだろう。
少し話がそれるが最近”親ガチャ”なる言葉が流行っているそうだ。
オンラインゲームやスマホゲームで希望のアイテムを入手するために、クジを回すことを「ガチャ」と呼ぶが、それを自分の人生になぞらえたのが”親ガチャ”らしい。ガチャは基本的にくじ引きであるため、その結果は運次第。自分の出生もそれと同じで、どんな親の元に生まれてくるかを選ぶことはできない。
翻って、自分の人生がうまく行かないとしたら、”親ガチャ”に失敗したせいであり、自分の責任ではない、という意味合いが込められている。
実はこの”親ガチャ”に関しては、古代ギリシャの哲学者セネカが著書「人生の短さについて」ですでに述べている。
「我々がよく言うように、どんな両親を引き当てようとも、それは我々の力でどうすることもできなかったことで、偶然によって人間に与えられたものである。」
まさに”親ガチャ”と同じ考え方がすでに古代ギリシャにて広まっていたということだろう。
そのような考え方について、セネカは直後にこう述べている。
「とはいえ、我々は自己の裁量で、誰の子にでも生まれることができる。そこには最もすぐれた天才たちの家庭がいくつかある。そのどれでも、君が養子に入れてもらいたい家庭を選ぶが良い。(中略) 彼らは君に永遠への道を教えてくれ、誰もそこから引き下ろされない場所に君を持ち上げてくれるだろう。
これは死滅すべき人生を引き延ばす、いな、それを不滅に転ずる唯一の方法である。」
ここでセネカが述べている”家庭を選ぶことができる”というのは、過去の優れた人物の書物を読み、彼らと親子のように真剣に語らうことを指したものだ。
セネカはこの書の中でいかに人生が短いかを説き、一瞬たりとも無駄に過ごしてはならないゆえんを何度も反芻する。そのための具体的な方法として、古代の偉大な英知が残した名著を読むことを強く勧めている。
「われわれはソクラテスと論じ合うこともでき、エピクロスとともに安らぎを得ることもでき、ストア派の人々とともに人間性を打ち破ることもでき、またそれをキュニコス派の人々とともに乗り越えることもできる。
自然がどんな時代とでも交わることを許してくれる以上、この短くも儚く移り変わる時間から全霊を傾けて自分自身を引き離し、あの計り知れない、永遠な、また我々よりもすぐれた人々と共有する事柄に没入しないでよいであろうか。」
(セネカ「人生の短さについて」)
本との正しい向き合い方
では、我々はどのようにして本を読むべきなのだろうか?
私は昭和の文筆家・福田恆存 (ふくだ つねあり) の考えが最も真に迫った表現ではないかと思う。
福田は言う
「本を読むことは、本と、またその著者と対話することです。」
「本は、問うたり、答えたりしながら読まねばなりません。要するに、読書は、精神上の力くらべであります。本の背後にある著者の思想や生き方と、読む自分の思想や生き方と、この両者のたたかいなのです。」
著者が述べることを唯唯諾諾と受け入れること、あるいは極端に自己本位に読み進めることは対話とはなりえない。著者の主張を言葉尻だけでなく、思想的に捉えるのと同様に、自らの思想や生き方とも比較考量しながら、真剣に検討していく。
これが100%正しいのかどうかはケース・バイ・ケースかもしれない。
しかし、著者の述べるキーワードや結論だけをつまみ食いして分かった気になるような読書よりも、著者の主張が自分の心に沈潜するような深い読書ができるようになるのは間違いないと思う。それでこそ一生のうちの貴重な時間を読書に割く価値が生まれるのではないだろうか。
「アウトプット」という近視眼的な結果を得るために、それをないがしろにするのは如何にも愚かな行為だと言わざるを得ない。
読者に疲れた人たちへ。
以上、本を読むということに関してつらつらと書いてきた。
ここまで書いておいて言うのも変な話だが、本来、本の読み方は自由だ。
いつ、どのように、どんな本を読むのか。
速く読むことも遅く読むことも自由だ。
それを否定するつもりはない。
だが、自由にはすべからく責任が伴うことも事実だ。読書においては、その責任を意識することで、より著者と深く対話ができるようになるという側面がある。
昨今世間に流通している読書法の多くは、その本から得た知見を短期的に、そして文字通り"明文化"することを求められることが多い。
だが、明文化できることがその読書体験から得た物すべてとは限らない。むしろ読了後すぐに明文化できることなど、読書から得られた価値のほんの一部に過ぎない。
だから、本を読み終わった後に、その読書の成果を形にできなくとも何も問題はない。著者と十分に対話して感じ取った思想、対話の記憶は、その後じんわりとあなたの心に染み渡っていく。そして何年か後には、確実にあなたの心や思想を形成するとしてあなたの魂に宿るはずだ。
本当の読書の醍醐味はそこにある。
もし早く、効率的に読書をすることに疲れた人がいるなら、その読書の醍醐味をもう一度思い出してほしい。
そしてどうか著者と全霊を傾けて対話する楽しみを味わってほしい。
それ以外のことはどのようなことも読書においては枝葉末節に過ぎないのだ。
というわけで。
今回も長文を最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m
教養ブームが生む弊害について。教養とは”思いやり”である。

コロナ禍に前後して活況を呈するのが”教養”市場だ。
日本人の勉強好きは昔からの特徴だが、社会の不安定化を反映してか、単なる勉強を超えた"教養"という分野が注目を集めている。
たとえば書店の入り口を潜れば、真っ先に教養コーナーが目に飛び込んでくるなんでこともしょっちゅうだ。
そこに並べられている本を見れば
「教養としての地政学」
「教養としての地理」
「一日一ページ、読むだけで身につく世界の教養」
なんて本まである。
先の読めない社会状況が続く中、手軽に、しかし確実に教養を身につけたい。そんなニーズに応えようとする本がどっさりだ。
けれども、そもそも教養とは何だろうか。
「あの人は教養があるね」などと言われれば何だか頭が良さそうな、でも嫌味のない、上品な知性が身についた人のよう。
そんな何だか誇らしげになる魅力がたっぷりの"教養"だが、そもそも知識や知性とは何が違うのだろうか?
私自身は「教養人です」「教養とはこれだ」と胸を張って言えるような教養は持ち合わせていない。
だから「これをやれば教養が身につく」などと偉そうにアドバイスするつもりはない。
ただ、そんな私でも現在の本や動画で教養が身につけようとする危うさを直感するくらいの常識はある。
今回は教養について多少の所見を述べることで、教養ブームに乗っかることの危うさについて感じてもらえれば幸いだ。
さて、「教養とは何か」という問題を考えるときに、いつも思い出すのが福田恆存の言葉だ。
福田は「私の幸福論」の中で”高い教育を受けた人ほど教養がなく、現代文明の先端をいく都会人ほど教養がない。”と述べた上で、とある電車内で「窓を開けたいと思うが、迷惑ではないか」と丁寧に聞いてきた、「おそらく小学校くらいしか出ていない」老女の方がずっと教養があるのではないかと書いている。
福田はこの女性の何をもって「教養がある」と考えたのだろうか?
この女性が"窓を開けるときには、まず他人の同意を得てからでなければならない"という一般常識を弁えていたからだろうか?
そうではあるまい。
福田はこの女性の”他者との関係性を理解し、それに適した対応をする”という行動、あるいは行動規範を備えていた点に対して、教養を見出したのではないだろうか。
福田が見たところでは、この女性にはいわゆる”学”はなかったようだ。だが、彼女は社会を構成する一員として彼我の関係性を慮る謙虚さと、それを実践する礼儀は備えていた。その点にこそ福田は教養の姿を見出したのであろう。
そして、まさにこの点にこそ「教養とは何か?」という問いの答えが隠されているのではないだろうかと思う。
教養が単なる知識と違うのは、知識がその活用に他者の存在を必要としないのに対し、教養は他者との関係性を前提として価値を持つ点だ。
他者との関係性を理解すること、その関係性に応じた対応をすること、これらはいずれも人間社会の中で、人々がお互い心地よく暮らしていくための知恵”に他ならない。他者の存在を前提とした上での知恵、そして規範を身につけ、時季や状況に応じて柔軟に対応できること。それこそが”教養がある”ということではなかろうか。
だからこそ私達は”教養がある人”という言葉に、単なる知識の豊富さや、勉学で身につけられる専門性を超えた品格を感じるのだろう。
そのように考えると昨今の”教養ブーム”がいかに浅薄なものかが窺い知れる。
教養が他者との関係性を前提にするのならば、その関係性における適切な行動とは、現出した情況によって全く異なるものであり、いついかなる時にも適用されうる回答は存在しないことになる。したがって、知識ではなく”教養”を身につけたいのであれば、自分と他者との関係性を見抜ける力、すなわち他者の”人となり”を見抜く洞察力と、その関係性に適した対応ができる人間力 (経験や場数と言っても良いかもしれない) を磨かなくてはならない。
残念ながらそのような力は本や動画を目を皿のようにして見回しても、身につけることは不可能だ。さまざまな立場の人々と出会い、その人々の考えやお互いの関係性に思いを馳せること、すなわち”思いを遣わす”という意味での「思い遣り」の心をもつことこそが真の教養を身につける上では何より大事なことではないだろうか。
その意味では、昨今の教養ブームは単なるビジネス的利益の追求による教養の形骸化だけでなく、真に教養を身につけたい人を本来の教養から引き離す悪弊になるのではないかという気がしてならない。
今回も長文を最後までお読み頂きありがとうございましたm(_ _)m
鈴木宣弘「農業消滅」。日本を襲う飢餓までのカウントダウン。

現代は飽食の時代だと言われるが、その一方で日本は食料自給率は世界でも低い。
その自給率は実に38%。
私達が普段口にしている食料のうち、4割未満しか国内の生産量で満たせていない計算だ。
食は体の素だと言われるが、その意味では私たちの身体の三分のニが海外の食に依存していることになる。
この状況で、何らかの事情で食料が輸入できなくなったり、海外農産物の価格が高騰したらどうなるだろうか。
食料価格の上昇で済めばまだ良い。将来的には、日本で飢餓が発生する危険性すらある。
多くの人が大袈裟な絵空事だと思うだろう。
だが、2035年にはそのような飢餓状態に陥る危険性があると警告するのが、東京大学大学院教授、鈴木宣弘氏の著作「農業消滅」だ。
野菜の自給率は4%にまで下落
この本の中で著者は、2035年には日本は飢餓に直面する可能性があると指摘している (農林水産省のデータに基づく著者の試算)。
たとえば、現状では80%の国産率を誇る野菜も、実はその元になる種の90%が海外依存である。それを考慮すると現在でも自給率は8%程度。2035年には4%程度まで下落するという。
また、同様に牛肉は4%、豚肉1%、鶏卵1%などなど・・・2035年の国内自給率は恐るべき低さが見込まれている。
食料自給率が低い理由
なぜこれほどまでに日本の食料自給率は低いのだろうか。
有り体に言えば「農業が儲からない」からである。
収益さえ上がれば農業従事者も増え、投資も呼び込める。
そうならないのは「農業が儲からない」からであり、儲からないのは「日本の農業の生産性が悪い」からだ。
だから、日本政府は”強い農業”、”稼げる農業”を掲げて、農家の生産性を上げ、国際的な競争力を高めよう!
これが世間一般に流通している通説であり、それに則って政府も農家を鼓舞している。
しかし、残念ながらここには根本的な誤解がある。
それは「そもそも農業の目的とは国民を飢えさせないことであり、お金を稼ぐことではない」ということだ。
日本の農家は”守られなさ過ぎている”
日本では農家が競争から守られ過ぎているという批判があるが、実はこれは全く的はずれだ。
農家の農業所得に占める国の補助金の割合は2016年の統計で日本が30%であるが、諸外国ではどうだろうか?
実は、スイスが100%、ドイツが70%、イギリスが91%、そしてフランスが95%となっている。
つまりEU主要国においては、農家の所得のなんと90%以上が国家による負担、いわゆる税金で賄われているのだ。
また、諸外国から食料を輸入する際の関税率も日本は高いと思われているが、これも昔の思い込みに過ぎない。
OECDのデータによれば、日本の農産物の関税率は平均で11.7%と低く、多くの農産物輸出国の1/2から1/4程度である。(本書P135 )
世間の思い込みとは裏腹に、日本の農家は世界でも類を見ないほど”保護されていない”のが実情だ。
なぜ食糧危機が注目されないのか?
だが、このような日本の農業の実情を知る人はほとんどいない。
大きな理由の一つは「目の前に大量の食料があるから」だろう。
コンビニや飲食店でも大量の食べ残しが廃棄されているのを目にすることはあるが、「食料が不足しているので料理が提供できない」などという話は聞いたことがない。
また、ニュースなどで目にするのも「食料の大量廃棄」という問題がほとんどであり、日本が飢餓に直面する可能性があるなどという記事はほぼ流通していない。
それは日本の自給率の低さを補うだけの食料輸入を行っているからである。
冒頭でも書いたように、日本の食料自給率は38%。つまり、私達が普段口にしている食料のうち、6割以上は海外からの輸入に依存している。
もしこのような状況で、何らかの事情で食料が輸入できなくなったり、海外農産物の価格が高騰したらどうなるだろうか。
残念ながらこれは絵空事ではない。
今回のコロナ禍で明らかになったように、日本や海外の物流網が寸断されるような事態がいつ起こっても不思議ではない。
また、昨今の異常気象による影響も重要だ。たとえば中国では干ばつや害虫の大量発生により食料不足が深刻化している。中国政府は食料輸入を増やして不足分を補う方向だが、その場合、日本が輸入する食物が減少するという予測がある。
経済規模では世界第二位の大国となった中国と”二位と歴然とした差がある”第三位の日本。
もし食料確保の競争となった場合、どちらに軍配が上がるかは火を見るより明らかだろう。
飢餓を防ぐためにやるべきこととは?
早ければ2035年までに訪れる日本の食糧危機。それを防ぐにはどうすれば良いのだろうか?
それはこの本の副題「農政の失敗がまねく国家存亡の危機」が示唆している。
国家をあずかる政府にとってもっとも重要な仕事は、国民を飢えさせないことだ。
そのためには食料自給率の低さは喫緊の課題である。
諸外国はそれが分かっているからこそ、農家に多額の補助金を支払って彼らの生活を支えている。一方の日本は”稼げる農業”などと言って、農家への補助金を切り詰めひたすら自助努力を促進しようとする。
現在の日本の食料自給率の低さとは、このような国家の農業政策の失敗の当然の結果なのだ。
「国民を飢えさせない。」
この当たり前の国家の最重要目的を遂行し、国民を守るためには、それに十分な生産力を回復できるまで国がちゃんと農家を保護すること。これしかない。
稼げる農業などという絵空事は、その次の話なのだという当たり前の認識を取り戻すことが何より重要ではないだろうか。
という訳で今回ご紹介した本はこちら。
鈴木宣弘氏の著作「農業消滅」でした。
今回も長文を最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m
”普遍性のディズニー”と”多様性のチャップリン。あなたの心をつかむのはどっちだ?

世界で最も有名なこの二人だが、彼らの繋がりを知る人は意外にも少ない。年齢で言えば一回りほども違うが、実は彼らは強い師弟関係で結ばれていた。
たとえばこんな話がある。
ディズニーは子供時代からチャップリンに憧れて育ったが、二人が初めて出会った時、ディズニーはまだ駆け出しのアニメ・クリエイターでしかなかった。
だが、チャップリンはディズニーの才能をすでに見抜いており「君はもっと伸びる。君の分野を完全に征服する時が必ず来る」と予言した。その上でディズニーのその後を左右する重大なアドバイスも与えていた。
そのアドバイスとは「自分の作品の著作権は他人の手に渡しちゃだめだ。」というものだった。ディズニーと言えば、その著作権管理の厳しさで有名だが、そのポリシーには実はチャップリンのアドバイスが生きていたのだ。
・・・などと偉そうに言うものの、恥ずかしながら私もそのような二人の繋がりは全く知らなかったどころか、二人に対してあまり興味がなかったというのが実際のところだ。
そんな私が二人の繋がりを知ることになったきっかけが、偶然見付けたこちらの新書
大野裕之著「ディズニーとチャップリンーエンタメビジネスを生んだ巨人ー」。
本書は、ディズニーとチャップリンをエンターテインメント界の巨人へと昇華させた”キャラクタービジネス”を切り口としながら、彼らのエンターテインメント哲学の共通点と相違点を論評している。
前半は二人が歩んだ人生や、師弟関係とも言える二人の繋がりを20世紀前半の世界情勢を交えながら紹介する内容。「ディズニーとは」「チャップリンとは」と人に語れるようなちょっと深いウンチクを得ることができる。
一方後半では、二人の思想や世界観の違いを論評する。
ディズニー帝国とも言える巨大企業に成長したディズニーに比べ、チャップリンは残念ながら「昔の喜劇王」という印象が拭えない。しかし、今でもその映像を見た人の心を掴み、特別な感情を抱かせる圧倒的な存在感と魅力を放つのは多くの人が知るところだろう。
ディズニーとチャップリン、この二人の巨大な才能の共通点と相違点を考えることで、現代メディアとエンターテインメントの姿が立体的に見えるようになる。ディズニーやチャップリンに興味がなくとも楽しめる、知的興奮を味わえる新書だ。
- 二人の共通点”キャラクタービジネス”
- チャップリンの考えを一変させたカルメン裁判
- 著作権の重要性を認識したチャップリン
- 世界の人々と一つになるためのキャラクター
- 二人のアプローチの違い。「普遍性」と「多様性」。
- ディズニーとチャップリンの優劣をつけるのは愚問
二人の共通点”キャラクタービジネス”
ディズニーとチャップリン。
この二人の共通点として著者が挙げるのが「キャラクタービジネス」だ。
チャップリンと言えばほとんど人があの「チョビ髭、山高帽子、不格好なスーツ、そしてステッキ」という映像を思い浮かべるだろう。一方のディズニーはミッキーマウスを筆頭に現代でも数多くのキャラクターを取り揃えている。
今では当たり前となったキャクタービジネスだが、この原型を生み出したのが他ならぬチャップリンだった。
キャラクタービジネスと言えばあまり良いイメージを持たない人も多いかもしれない。いわゆる”著作権”を笠に着て、他人が作り出したものに言いがかりをつけて法外な賠償金をせしめるような悪どいビジネスが横行しているのを目にしたことがある人も多いだろう。
キャラクタービジネスの根幹にあるのは、キャラクターというものに著作権があるという概念だ。今では当たり前の考えだが、昔は現在の中国のようにキャラクターというものに対する著作権という概念はまったく存在しなかった。
チャップリンの人気が高まりはじめていた当時は、映画という新しいメディアが産声をあげた頃だったのだが、まさにこの映画の興隆こそがチャップリンに”著作権によるキャラクター保護”の重要性を痛感させたのだった。
そのきっかけになったのが「カルメン裁判」という裁判だ。
チャップリンの考えを一変させたカルメン裁判
このカルメン裁判を簡単に紹介すると、チャップリンは当時エッサネイ社という映画配給会社で監督、脚本、主演をすべて担当しており、いくつかの大ヒット作を生み出した。その後チャップリンは別の会社に移籍したのだが、なんとエッサネイ社がチャップリンの作った「チャップリンのカルメン」という映画を改変して、別の映画として公開したのだ。チャップリンはこの映画の差し止めを要求したが、裁判によってチャップリンは敗訴する。おまけに、このエッサネイ社がチャップリンがいなくなったことによる損失を損害金として賠償する裁判まで起こした。その後も、「チャップリンとカルメン」以外の作品も同じように再編集を行い、別映画として公開したようだ。
その上、そもそもチャップリンが移籍したことで損害を受けたという”難癖”によって、チャップリンに多額の賠償金を負わせる裁判まで起こされている。
著作権の重要性を認識したチャップリン
この一連の裁判によって著作権を自分のものにすることの重要性を認識したチャップリンは、その後自前の撮影所を建設し、自分で経営を担うことにした。会社の庇護や金銭的条件よりも、自作の著作権を優先したわけだ。
著作権トラブルによって、その大切さを骨身に染みたチャップリンは映画の著作権の確立に一役を買った。だからこそチャップリンはディズニーという偉大な才能に出会った時に、まず著作権保護の重要性をアドバイスしたのだった。
今でこそ当たり前となったこのキャラクターの著作権保護をチャップリンがはじめたのは、現代のような興行収入の保護だけでなく、まさにクリエイターの良心と権利を守り、彼らが創作に集中できる環境を整えるためだったのだ。
さて、同じキャラクターをビジネスとして活用しながらも、その方法論はディズニーとチャップリンでは全く異なっている。
「チャップリンは、キャラクターの権利を確立した最初の人物である。だが、意外なことに彼はそれを主たるビジネスとして展開することに興味はなかった。あくまで思う存分に作品作りに集中するために、すべての権利を完全にう手中におさめ、その一つがキャラクターの権利だったわけだ。
(中略)
それゆえに、驚くべきことに1920年代以降のチャップリン全盛期に夜に出たおびただしい数のキャラクター・グッズはほとんど無許可で販売されたものだった。チャップリンは”偽チャップリン俳優”には厳しく対応したが、関連グッズは放置していた。彼は根っからのクリエイターだったのだのだ。」(本書P261)
では、一方のディズニーはどうだったか。
ディズニーと言えばミッキーマウスが代表格だが、白雪姫やくまのぷーさん、アナ(と雪の女王)などなど、数多くのキャラクターを取り揃えている。それは自社で生み出したものだけでなく、スパイダーマンやアイアンマンなど他社を買収することによって獲得したものも含まれる。
その上、それらのキャラクタービジネスから得た利益で巨大企業を次々の買収し、知的財産を次々と獲得。たとえば、映画配給会社の20世紀フォックスを買収し、自社のDisney+というストリーミング・サービスで膨大な映画や番組を独占して配信するようになったこともその一つ。メディア・ネットワーク事業を基幹産業として、年間14兆円を叩き出すコンテンツ企業になった。
キャラクタービジネスを基盤に、ディズニー帝国とも言える巨大産業を生み出したのだ。
世界の人々と一つになるためのキャラクター
同じキャラクタービジネスでありながら、なぜ具体的な手法にこれほどまでの違いが出たのだろうか?
著者はその原因を「ディズニーの”普遍性”」と「チャップリンの”多様性”」という違いに見出している。
この二人の特性の違いをはっきりさせるためには、迂遠なようだが二人が目指した共通の理想について考えると分かりやすい。
著者は本書第4章において、チャップリンの言葉を引用しながら次のように語っている。
(チャップリンと言えば多くの人が思い出すように、無声映画を作り続けた。いわゆる出演者の”声”のないパントマイムのような映画だ。一方当時は音声のある”トーキー映画”も出はじめており、将来的にはトーキー映画の方が主流になると言われていた)
「チャップリンが、1931年に『街の灯』を、すでに時代遅れとみなされていたサイレントで作ると発表した時、多くの批評家が驚きを示した。彼は『パントマイムとコメディ』という文章を発表して、彼らの疑問に答えようとした。
”なぜ私は無声映画を作り続けたか? 第一に、サイレント映画は普遍的な表現手段だからだ。トーキー映画にはおのずと限界がある。というのも、特定の人種の特定の言葉に規定されてしまうからだ。”
チャップリンがこだわったのは、サイレントかトーキーかという技術ではなく、世界中の人に理解されるかどうかだった。その考えこそ、ディズニーも共有しているものだった。」
(本書P121)
「ミッキーはほとんど一夜にして国際的な成功を収めた。なぜなら、初期の作品においては、その笑いの大半が目で見てわかるギャグだったからだーローレル&ハーディやバスター・キートン、そして特にチャーリー・チャップリンのように。人々が香港で見ていても、パリでも、カイロでも、言葉が必要ない。彼らは、スクリーンで起こっていることを、ただ笑うことができるのだ。」
(本書P123)
世界中の人々に言葉や人種を越えて、笑いや感動を伝えたい。
ディズニーもチャップリンもその思いを共有していた。
だからこそ二人は「世界中で通じるたった一つの共通イメージ」の重要性を鑑みた結果、”キャラクター”にこだわったのだ。
二人のアプローチの違い。「普遍性」と「多様性」。
世界中で通じるたった共通イメージを作り上げるために”キャラクター”を重要視したその思想は、二人に共通するものだった。
しかし、具体的なアプローチはまったく違う。
それが前述の「ディズニーの”普遍性”」と「チャップリンの”多様性”」である。
著者はディズニーの源泉はその普遍性にあるという。
たしかにディズニーのキャラクターたちが世界各国で通じる普遍性を持っているのは間違いない。だが、この場合の普遍性は少し意味合いが異なる。
ディズニーの場合は、ディズニーランドのようにまず現実世界と全く切り離された”夢の国”を構築する。そのクローズドな世界の中での唯一無二性をキャラクターに付加するという手法をとる。そのため、ディズニーキャラクターの普遍性とは、あくまでそのキャラクターのために構築された架空の世界の中で効力を発揮するものになる。
だからディズニーのキャラクターがどこかの国やサービスに提供される際には、必ずその世界観と一緒にパッケージされることになる。言うなれば、キャラクターが普遍的な価値を持ちうる世界ごと販売する形態、それがディズニーのキャラクタービジネスである。だからこそ、ディズニーは他者によるキャラクターの侵害に極端にシビアな態度を取るのだと言えよう。
これに対してチャップリンのキャラクターは、そのキャラクターの普遍性ゆえの多様性を持っている。
例えば「インドのある村ではチャップリンがヒンドゥー教の神々の一人として祀られ、喜劇王の誕生日を聖日として村全員でチャップリンの紛争をして練り歩く風習がある」(本書P271)。
また、香港などでも「香港のチャップリン」として活躍する俳優がいるが、その風貌や実際の映画は本物のチャップリンとは似てもにつかないものだ。それでも現地の人たちは「これがチャップリンだ」という共通のイメージを抱いている。
著者はそのような現象が起こる理由として、チャップリンが持つ”内面に宿る大衆的リアリティ”を挙げる。
曰く
「放浪紳士チャーリーは、寓話的な外見を持つが、その内面は大衆のリアリティに根ざしている。チャーリーは現実社会を孤独に放浪し、一つの場所に留まることはない。夢を見ているが、かなえられることは決してないし、その恋は必ず破れる。孤独に理想を求め続ける彼は、権力に対してささやかない反抗を試みる弱者の一人だ。そうした内面ゆえに、チャーリーの精神は時代を超えて生き続ける。」(本書P277)
つまり、チャップリンには現実社会に生きる人なら誰しも抱える、悲哀や孤独といった普遍的テーマを体現している。だからこそ世界の人の心をつかむ。そして、そのテーマは価値観の違いによってさまざまな解釈とアプローチで描かれる。
ディズニーはキャラクターを夢の国という虚構の枠組みに収めることで、世界に通じる普遍的パッケージを生み出した。一方のチャップリンは、現実社会に生きる人々に共通する普遍的テーマを取り扱うことで、様々な価値観の持つ多様性を尊重した。
”世界中のどこででも通じる普遍性”を目指しながらも、ディズニーとチャップリンはまったく違うアプローチで迫ったのである。
ディズニーとチャップリンの優劣をつけるのは愚問
本書の最後に著者は「この本では二人の差異を強調」したものではない、と言っている。
ましてやどちらが優れているかといったような優劣を図るような内容では決してない。
だが、本書を素直に読めば著者が”多様性”を重視したチャップリンの方をより高く評価しているのは疑いようがないと思う。
実際、私も今回のブログを書いている中で、やはりチャップリンの方を好意的に書いているのは否めない。ただ、それは必ずしも「多様性を重視したチャップリンの方が正しい」というような善悪二元論ではない。
たしかにディズニーは虚構の世界を作り上げることで、世界のどこででも売れる普遍的パッケージを生み出したのは間違いない。それに比べれば現実社会のリアリティを追求したチャップリンの方が芸術としての価値は高いようにも思える。
だが、ディズニーは虚構の世界を作り上げ、世界の人々にその夢を見せることで、多くの人に夢と希望を与えているのは事実だ。それによって現実社会の生きづらさをかろうじて耐え忍んでいる人もいるだろう。そういう意味ではディズニーはチャップリンよりも多くの人の心を救っているかもしれない。
ディズニーとチャップリン、これだけの巨大な才能が並べられると、つい二人の優劣をつけたくなってしまう。
だが、それは最も愚かな行為だろう。
私達が二人から学ぶべきは「世界に通じるコンテンツを作り上げる」という一つの目標であっても、思想や哲学によってそのアプローチにはさまざまな切り口があるのだということ。そして、様々なアプローチがあるからこそより多様な社会が築かれるのだということだ。
普遍性と多様性、どちらが欠けても本質を見失ってしまう。
常に異なる視点から物事を考える柔軟性を持つことの大切さ、そしてそこから見えてくる世界の面白さをこの本ではきっと感じてもらえると思う。
という訳で今回ご紹介した本はこちら。
長文を最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m
自由と平等という幻想が社会を狂わせる。ジョン・ロック「市民政府論」
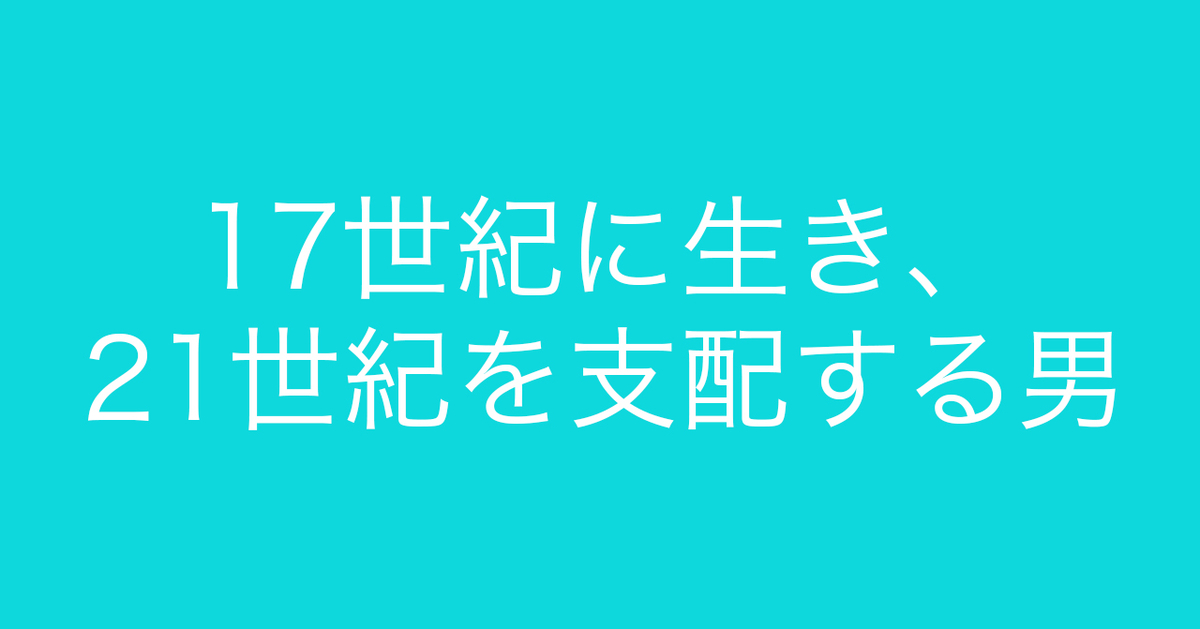
「国民の信任を得た」
選挙後に多数派となった政党がよくいう言葉の一つだ。
だが、この言葉にもやもやした違和感を感じる人も多いのではないだろうか。
「国民の信任を得た」と言うけれど、投票した人がみなその人に投票したわけではない。むしろ「こいつだけは信任したくなかったのに」と思う人も大勢いるだろう。
本来選挙に勝つことと、信任を得ることは別の話のはずだ。それなのに、なぜわざわざ「信任を得た」と表現するのだろうか?
ここには歴史上のある人物の政治思想が深く関係している。
それが17世紀の政治哲学者ジョン・ロックが提唱した"社会契約"という思想だ。
思想家の丸山真男はロックを評して「17世紀に生き、18世紀を支配した人物」だと言った。しかし、彼の著作に目を通すと、今の私たちの思考の多くがロックが作り上げた土台の上に築き上げられていることに気づく。
その意味では、ロックは「17世紀に生き18世紀を支配した」どころか、「21世紀を支配している人物」だとさえ言える。
今回は彼の主著「市民政府論」を元に、私たちの思想や考え方がいかに17世紀的な価値観に縛られているのか。それが現代社会にどのような影響を与えているのかを考えてみたい。
- 著者紹介
- ロックを知る上での基礎的概念
- 17世紀に生きたロックが21世紀を支配する構造
- 誰も信頼していないのに「信任」されるという矛盾
- 信任してないのに統治される?
- 社会契約論の欠陥
- ロックが”証拠なし”でも社会契約論を生み出さなければならなかった理由
- 今こそロックを乗り越えなければならない。
著者紹介
ジョン・ロック。1632年生まれ、1704年没。イギリスの哲学、思想家。
家柄は下級官吏であり名門の家柄ではなかったが、さまざまな人の手助けによって名門校ウェストミンスター・スクールやオックスフォード大学に進学。ギリシャ語や修辞学、医学、物理学を学ぶ。
有力な政治家であったシャフツベリ伯爵と懇意になったことで政治の道へ。一時オランダへ亡命するなど波乱の時期もあったが、帰国後には「権利の章典」の草案に関わるなどイギリス政治の中心に積極的に関わる。主著「市民政府論」「人間知性論」で思想家としての名声を確立した。
1704年、イングランド東部のエセックス州にて肺疾患により死去。享年72歳。
ロックを知る上での基礎的概念
ロックの現代社会への影響を考えるためには、ロックが示したいくつかの概念を知っておいた方が話が理解しやすい。まずはロックの基礎的な概念をサラッと紹介したい。
自然状態
天然自然で人間がどのような状態にあるか? を想定したもの。
この時代の哲学者の多くが独自の自然状態を定義しているのでややこしいが、ロックの言う自然状態とは
「個人一人ひとりが完全に自由で、完全に平等な状態。ここでは、自然法の範囲内で自分が正しいと思う範囲で自分を律して行動する。 自分の行動に対して他人の許可は必要ないし、他人の意思に依存することもない。」
ということを意味している。
このように書くと「誰もが好き勝手なことをやって良い」と言っているようだが、そうではない。当時はまだキリスト教の価値観が有効であった。だから、人間が自由であれば自然と神の意思に基づいた理性的な行動を行うため、皆が自分勝手な行動を犯すことはあり得ないという前提に基づいている。
自然法
これは上記のような自然状態において、人間が従うべき法律のことだ。天然自然の状態なのに従うべき法律があるというのもおかしな話だが、ロックの中では矛盾していないようだ。
これもやはりキリスト教的な考えに基づいており、まずこの世界は神が作ったものであり、人間はその世界で生まれた。だからどんなに自然な状態と言えども、神が示す理性的で、道徳的であるべしという”自然法”には人間は規定される。
いくら自由であると言っても、他人の財産や安全を脅かしたり、傷つけたりすることはあってはならない。これが自然状態であっても従うべき法律、すなわち”自然法”だ。
所有権
今では当たり前の「所有権」という概念だが、当時はまだそれほど一般的ではなかった。特に「土地」が顕著だが、国王や領主、あるいは神のものであり、個人がそれを所有できるという考えは当時は比較的新しいものだった。
ただ、ロックがオリジナルで考え出したアイデアというわけではない。
時代的には、お金によって土地を所有する、いわゆる”土地持ち”が出現しはじめており、所有権的な考えは広まりつつあった。ロックはあくまでその正当性を理論的に定義づけただけだ。
それが本当に”理論的”であったかどうかは議論の余地があるが、本稿ではそこまで深入りしない。
社会契約
恐らくこの「社会契約」こそが、ロックが示した概念の中でももっとも重要なものだ。
上記で示したように、ロックによれば自然状態において人間は一人ひとり、完全に自由で、平等であり、その精神や所有権は誰にも拘束されることがない。
その個人がなぜ他の人と集まり、共同体や国家を作るのだろうか?
それは個人であればたしかに自由ではあるが、生命や財産の安全性が確保できないからだ。それを守るために個人は、自分の自由の度合いをある程度制限してでも共同体に属することを選択する。そして、共同体は個人の自由を制限する代わりに、その安全を守るための行動を行う。
つまり、個人と共同体はそれぞれの利益のために”同意”に基づいた契約を行うのだ。
これがロックの言う「社会契約」だ。
以上、非常にざっくりとした形だがロックが示した重要な概念をさらってみた。これらはどれも非常に有名な概念であり、現代社会を理解する上でも重要な知識だ。ネットで探れば詳しい解説がいくらでも転がっているので、興味がある方はぜひ探ってみてほしい、
17世紀に生きたロックが21世紀を支配する構造
さて、ではこれらのロックの概念が一体どのようにして現代社会にも大きな影響を与えているのだろうか?
ここに「私達の”信任”の下に政府は国家を統治している」という、冒頭で述べた信任の問題が浮かび上がってくる。
ロックによれば、私たちは独立した個人としてこの世界に存在している。現代の私たちもそのように教えられて来たし、そう信じている人がほとんどだろう。では、なぜ独立した個人として存在するはずの私たちが、政府の統治下に服さなければならないのだろうか?
その理由を、ロックは巧妙に説明した。
「人間はみな、本来的に自由で平等である。そして独立している。同意してもいないのにこの状態を追われるとか、他社の政治的権力に服従させられるとかいったことは、あり得ない。
(中略)
共同体を結成する目的は、自分の所有物 (生命・自由・財産) をしっかりと享有し、外敵に襲われないよう安全性を高めるなど、お互いに快適で安全で平和な生活を営むことにある。」
本書P138
もっと噛み砕いてみるとこうなる。
私達は本来、平等で自由な独立した個人として存在している。だが、自分の安全や財産を守るためには一人でいるよりも集団 (共同体) に属した方が良い。そのために私達は所有権や財産権などを部分的に放棄して、その共同体に属することを選択している。それが私達が社会と取り決めたことなのだ。
これが国民と社会との契約、すなわち「社会契約」である。
その上で、ロックはこの契約が成立するためには、私達国民が統治者が正しい行いをするという信頼・・・すなわち「信託」が必要だ述べている。つまり、私たちが本来持っている自由や財産を統治者(国家)に移譲するのは、統治者が私たちのために正しいことを行ってくれるはずだという信頼が基礎になければ成立しないということだ。
この社会契約論はロックやその後のルソーなどによってバージョンアップされているものの、基本的には現代の私達の社会、政治体制の基礎になっている。
冒頭で私がロックのことを「17世紀に生き21世紀を支配している人物」と書いた理由はここにある。21世紀に生きる私達は今もなお17世紀の哲学者ジョン・ロックが敷いた「社会契約論」から続くレールの上で生きているのだ。
誰も信頼していないのに「信任」されるという矛盾
ここまで読みといて来ると、政治家が選挙の時に「国民の信任」ということをしつこく繰り返す理由がわかって頂けると思う。
率直に言って多くの国民はの政治家のことを信じてもいない。選挙で投票する時も「まぁ、こいつなら少しはマシだろう」という程度でしか選んでいないことがほとんどだ。そんなことは分別のある政治家なら本人も分かっているだろう(本当に「信任された」と思っている人もいるだろうが・・・)。
だが現代社会が「政治家が国民のために正しい行いをしてくれると信頼して、政治権力を譲渡している」という社会契約論の延長線上にある以上、たとえ形式上のことであってもそう言わざるを得ないし、その形式によって現実の政治が曲がりなりにも機能しているのが実情なのだ。国民の信頼を得た・・・すなわち「信任された」という物語の上に現在の社会は成り立っているのだ。
だが、残念ながらこの内実を伴わない”形式上の信任”、”信任という物語”によって、たびたび私達の生活は混乱をきたすことがある。
信任してないのに統治される?
たとえば昨年からのコロナ騒動による政府の場当たり的な政策はその最たるものだろう。
日本は一応国民が主権を担う国民主権の国だ。だが実際にいまの菅政権は私たちが選挙で選んだ訳ではない。安倍前政権が突如として崩壊したため、その急ごしらえ的に生まれた政権。それが菅政権だ。言うなれば、誰も信任していない政府だ。
実際、毎日新聞が4月17日に報じた世論調査では、国民の菅政権に対する不支持率は62%を超え、戦後最悪を記録した。それにも関わらず菅政権は今もなお国民を導く立場にある。
菅内閣の支持率30%、発足以来最低 毎日新聞世論調査 | 毎日新聞
それにも関わらず国民はこの政府に従わなければならない。繰り返すが「国民主権の国」であるにも関わらずに、だ。
このような矛盾に満ちた社会が私たちが生きる現実だ。
社会契約論の欠陥
この矛盾の根幹はどこにあるのだろう。
実はそれもまたロックが述べる社会契約論という思想の中にある。
先にも書いたように、社会契約論は平等で自由な個人が、自分の財産を守るという目的のために統治者と同意の上で社会契約を結んでいる、ということになっている。
では、その同意は一体いつ行われ、いつ国民と国家は社会契約を結んだのだろうか?
その問いに対してロックは次のように答えている。
「ある国の領土のいずれかの部分を所有ないし利用している者はだれでも、そうすることによって暗黙の同意を与えているのであって、土地を利用している間はずっと、その国の方に服従する義務を負うのである。・・・土地の利用には・・・さまざまな形態がある。わずか一週間の滞在であっても、あるいは単に街道を自由に往来するだけであっても、土地を利用していることになる。」
(本書P171)
つまり、ある国の土地を一瞬でも利用したなら、その瞬間にその人は国家が統治することに同意し、社会契約を結んだことになるというわけだ。
だが、このような一方的な契約をはたして「個人の同意を得られた」とみなしても良いのだろうか?
ロックは、その土地を少しでも利用したならというが、それならばこの世に生を受けた瞬間・・・あるいは母親の胎内に生命を宿した瞬間から、その個人は国家と契約を結んだことになる。そこに「同意しない。」「契約を結ばない。」という自由はない。
そんな契約が果たして契約と認められるのだろうか?
ロックが”証拠なし”でも社会契約論を生み出さなければならなかった理由
実はこの点に関して、ロックは論理的な証明をしていない。
それどころか「個人の同意に基づく契約が行われ、それが共同体が発生することになったことを裏付ける歴史的実例がない」といい、自分の理論に裏付けがないことをロック本人も認めている(本書P143)。
それにも関わらずロックは「記録というものは共同体が創設された後につけられるものだから、共同体が創設される前の記録がないのは全く不思議ではない。記録がないからといって、そのような事実がなかったということはできない。」というかなり滅茶苦茶な理屈で、個人と国家の同意により社会契約が結ばれ、共同体が創設されたという持論を主張している。
普通に考えればこのような理論は誰からも受け入れないはずだ。
少なくともこのような滅茶苦茶な理論では、小論文のテストなら赤点必死だろう。
一体なぜロックはこのような無茶苦茶な理屈を採用したのだろうか?
さまざまな理由が考えられるが、一つ挙げるとすればそれは個人には完全なる自由と平等が生まれつき与えられているという価値観をロックが絶対的な命題として掲げたからだろう。
ロックが、個人は完全なる自由と平等を持つと信じている以上、あえてそれを放棄して共同体を形成するためには、それに足る目的を何とかひねり出さなくてはならなかった。その苦肉の策として考案されたのが「自らの安全と財産を守るために、個人の同意に基づく社会契約が行われ、共同体(国家)は形成された」という理屈だったのだ。
結論ありきで考え出されたようなめちゃくちゃな話だが、歴史を見ればこの理論は大成功だった。
ロックに続く数多くの思想家がこの考えから大きな影響を受けた。
21世紀に生きる私たちでさえも「自由で平等な個人が自分の安全を守るために国家に権利を委譲することに同意している」という社会契約論の基本理念を受け継いでいる。
今こそロックを乗り越えなければならない。
このロックの「同意に基づく社会契約」という理論は大きな問題を引き起こす。
それは国家の形成は「個人」の力と「同意」の力を現実よりも大きく見せてしまうことだ。これが正しいのならば、国民の同意が得られなければ国家は崩壊することになってしまう。
だが、現実にはそのようなことは起こらない。
私たちが日々感じているように、たとえ個人が同意せずとも国家や共同体の方針は決まっていく。むしろ「同意しない」という消極的な否定だけでなく、「そういう方針には反対する」と積極的な否定の態度を示したとしても、実際には個人の主張は無視されて物事は進んでいく。
それが現実であり、そのような現実の中で人間は必死にもがいて日々生きているのだ。
しかし、ロックの「同意に基づく社会契約」という理論は、そのような現実の矛盾を覆い隠してしまう。
今回のコロナ騒動の政府の場当たり的な対応がその典型だろう。
政府は「選挙によって選ばれた」こと、すなわち自分たちが統治することに同意を得たという形式を免罪符にして、国民に一方的な負担を強いる政策を次々と実行に移している。しかもそのどれもが実効性に欠けている。
それにも関わらず次の総選挙まで「国民の同意を得た」という形式になっている。
ロックは個人の同意に基づく社会契約によって共同体が形成されると言った。
しかし、現実には国家の方針は一般大衆の個人が全くあずかり知らぬところで決定され、それに同意を求められることすらない。たとえ政府の決定に疑問があったとしても、その命令には絶対に逆らうことはできないのだ。
私はロックが示したこの虚構の理論を乗り越えることが、いま非常に重要なのではないかと思う。
ロックの「個人の同意に基づく社会契約によって共同体が形成される」という虚構に縛られているからこそ、政治家は「選挙に勝てば(=形式的に同意を得られれば)やり放題」になるし、国民は「同意しようがしまいが、結局政治家様がやりたいようにやるんだから選挙なんか意味ない」という無力感にさいなまれることになる。
国家が個人との契約によって形成されているという虚構のシステムから解放されることで初めて、国民は「国家とは何なのか」「国家がまとまるには何が必要なのか」「何が国家を破壊するのか」「国家を存続させていくためには何が必要なのか」という政治家も国民が対等に、そして同じ目線で国の行く末に関わることができるのではないだろうか。
17世紀に生まれ21世紀にも影響を与え続けるロックの理論。
今こそその原点に改めて迫るべきではないだろうか。
というわけで、今回ご紹介したのはこちら
ジョン・ロック「市民政府論」でした。
今回も長文を最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m
なぜオリンピックを強行開催するのか。政府の基本方針から読み解く理由。

「政治家は一体何のために仕事をしているのだろうか。」
思わずそう呟かざるを得ないほど、現代は政治家と国民の分断が拡大している。
東京オリンピックの強行開催はその象徴的出来事だ。
朝日新聞が5月に発表した世論調査によると、「中止する」と答えた人が43%、「再び延期する」と答えた人は40%に上ったようだ。
多くの国民がオリンピック開催に反対する理由は極めてシンプル。海外の選手や関係者によって感染が拡大することを恐れているからだ。
政府あるいは国家の役割とは本来国民生活の安定と安全を確保することのはず。それにも関わらずなぜ政府はこれを強行しようとするのだろうか。
オリンピックの目的は何か
政府が東京オリンピックを強行する理由を読み解くのに参考になる資料がある。
首相官邸のHPに掲載されている「2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の 準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針」だ。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/kaigi/dai2/siryou1-2.pdf
これによれば東京オリンピックの開催意義を政府がどのように考えているかが分かる。
例えば
・自信を失いかけてきた日本を再興し、成熟社会における先進的な取組を世界に示す契機
・多くの先進国に共通する課題である高齢化社会、環境・エネルギー問題への対応に当たり、 日本の強みである技術、文化をいかしながら、世界の先頭に立って解決する姿を 世界に示し、大会を世界と日本が新しく生まれ変わる大きな弾みとする。
・文化プログラム等を活用した日本文化の魅力の発信、スポーツを 通じた国際貢献、健康長寿、ユニバーサルデザインによる共生社会、生涯現役社 会の構築に向け、成熟社会にふさわしい次世代に誇れる遺産(レガシー)を創り 出す。
と言った具合だ。
(一応、11ページある文書の10ページ目に「スポーツ基本法が目指すスポーツ立国の実現」という項目が一つだけある)
ここから読み取れる東京オリンピックの目的とは
「日本文化ビジネスの拡大」
「観光業促進」
「科学技術力アピールによる諸外国による投資の拡大」
といった、いわゆるビジネス的な金儲けであるということだ。
いわゆる一般的な国民が考えているような、国際平和や海外との交流といったスポーツの祭典として意義は全く考慮されていないのだ。
"オリンピック開催"という正義
オリンピックを推進する政治家たちは、たとえ世論を無視した強行開催であってもオリンピックを開催すればビジネス的には成功すると信じている。
そして、儲かりさえすれば今は文句を言っている国民たちも「やっぱりオリンピックをやって良かった」と手のひらを返すに違いないと高をくくっている。
だから民意をどうであろうと強行開催してしまえば良い。それが日本の未来のためになる。
言うなれば、彼らは”自分が信じる正義”に基づいて行動しているのだ。
彼らの正義が正しいのかどうかはここでは問うつもりはない。ただ、政治家として行政に携わる者たちには、たとえ民意を無視してでも自分たちが正義として信じる行動を国民に強制することができる"政治力"があること。
そしてそれは"民意によって選ばれた"という法的な正当性が付与されているということを、私たちは目の当たりにしている。
私たちはこれまで日本は法治国家であると信じてきた。そして法を通して私たち国民は主権を行使しているのだと信じてきた。それこそが近代国家のあるべき姿であると。
だが、本当にそうだろうか?
今回のオリンピックをめぐる騒動は、「オリンピックを開催するべきかどうか」という狭量な枠組みで収めるべき議論ではないのではないか。
私たちがいま目の当たりにしているのは、法による統治という理念の限界という、近代の政治哲学が静かに、しかし確実に孕み続けてきた問題なのではないだろうか。
だとすれば、今こそ私たちは近代という時代について考え直さなくてはならない大きな問題を突きつけられているのではないだろうか。
今回も長文を最後までお読みいただきありがとうございましたm(_ _)m
国民のために働きたくても働けない。「ブラック霞ヶ関」の実態

「官僚」
日本においてこれほど悪いイメージを持たれている言葉も少ないだろう。
本来なら日本を牽引するエリート集団であることを否定する人はいないだろう。その一方で多くの一般国民が抱くイメージとは
「上級国民の集まり」
「無駄に偉そう」
「税金から給料をもらっているくせに国民をバカにしている」
「まともな仕事をしてない(=まともな政策を作らない)」
といったものだろう。
そのようなイメージを覆すような衝撃的な本がある。それが今回紹介する
千正康裕「ブラック霞ヶ関」だ。
この本では、普段私たちが抱きがちな"上流階級"とは全く違う実態が描かれている。
超絶ブラック!官僚の実態
2019年に行われた官僚1000人のアンケートによれば、65.6%は年間残業時間が720時間を超え、1000時間超えが42.3%、1500時間超えが14.8%だった (ちなみに過労死ラインは960時間)と言われている)。
また、朝7時に業務開始時間、仕事が終わるのが27時過ぎというのもザラのようだ。
私自身も民間企業で同じようなスケジュールで仕事をしていた時期があるが、案の定体を壊して1年ほど休職せざるを得なかった経験がある。
著者によれば、厚生労働省や経済産業省などの本省で働く国家公務員に関して言えば、約一割が体調を崩して休職しているそうだ。
官僚と言えばれっきとした"エリート"。普通に考えれば「片手団扇」の生活をしていてもおかしくないはずだが、その彼らがなぜこのような殺人的業務をこなさなければならないのだろうか。
この本では元厚生労働省の官僚が自身の体験を交えながら
・なぜ官僚たちはこのようなブラック企業並みの働き方をしているのか。
・この官僚の実態が私たちの生活にどのような影響を与えているか
が解説されている。
その上で、私たちの生活をより良くするために官僚にどのように働いてもらうべきなのかについて、具体的な提案も交えて語られている。
一般国民にはあまり馴染みのない官僚たちだが、この本によりその生態や考え方を知ることで、どうすれば官僚たちが国民のために働けるようになるかが見えて来る。
そもそも官僚とは何か
官僚とはそもそも何だろうか?
Wikipedia的な説明をするならば、中央行政機関で各省にかかわる国家公務員のこと。特に国家公務員の中でも、国家公務員総合職試験で採用され、中央官庁の中で一定以上のポストにある人たちを指して官僚という。
公務員の中でも、国家公務員Ⅰ種採用試験という超難関試験を突破した者だけがなれる超エリート達だ。
彼らの仕事がどのようなものかをひと言でいえば、「官僚の仕事は政策をつくること」だと言えるだろう。
ではその「政策」とは何だろうか?
官僚が作る政策とは?
著者によれば政策とは「政府独自のリソースを活用して、人々の行動変容を促し、社会課題を解決する営み」のこと。
政府独自のリソースというのが分かりにくいが、たとえば法律による規制や税金の徴収とその配分。あるいは労働基準監督署による労働環境の取り締まりのような公的機関だけが実行できる手法のことだ。
これらを策定、運用する制度設計を行うのが官僚の仕事ということになる。
官僚の役割
このような政策とは私達一般国民の生活に直結するものだ。したがって、政策の設計をする際には、国民にとって利益があるように様々な現地調査や分析、それに基づく将来予測が必要となる。
当然ながらそれはインターネットで検索して、パソコンに入力すれば自動的にできあがるような単純なものではない。著者によれば「良い政策」を作るためには下記の3つのプロセスが重要となる。
1) 詳しい人が徹底的に考える
みなが使う法律や精度の案を作る人間は、その内容や変えた時の様々な影響が見通せるように詳しくないといけない。専門家の知識は非常に重要だ。
2) 出来るだけ多くの人の意見を聞く
仮に、指示下や官僚が優秀だとしても、世の中のすべての国民の生活や制度の欠陥を見通すことはできない。だから、色んな立場の人の意見を聞いて政策へ反映させることが重要。
3) 決めた後の執行のことをよく考える
どのような政策もそれが成立した時に大きな話題となるが、実際に重要になるのはそれが施行されてから。どれだけ大きな給付金を予算に盛り込んでも、それがちゃんと執行されて、国民に届くようにするための時間や手法を確保しなければ意味がない。
考えてみれば当たり前のことであり、どれも特別な意味を持つものではない。民間企業で働いたことがある人ならもちろん、学生であっても部活やサークルで何かを実行しようとしたことがある人なら、これらは実に当たり前のことだ。
ただ一つ注意しなければならないのは、これらのプロセスには非常な時間と労力、そしてお金がかかるということ。政策を考えるのはもちろん、多くの人の意見を求めるにも、政策のプロセスを精査するにも莫大な労力がかかる。
民間企業や学生のサークル程度ならその労力も知れているかもしれない。しかし、国の政策とは国民生活に強く、長い影響を与える (下手をすればその政策により生活が困窮するような可能性もある)。そして、一旦施行されれば、それを撤回することは容易ではない。
ここにこそ官僚がブラック化する原因がある。
すわなち絶望的な人員不足である。
日本は公務員が少なすぎる?
バブル崩壊以降、いわゆる”公務員叩き”が流行る中で日本の公務員はガンガン削られてきた。文字通りの人数削減もあれば、派遣労働者によって急場を凌ぐケースも多い。
一般的に日本は公務員が多すぎるというイメージがあるが、実は先進国の中では日本の公務員は圧倒的に少ないのが実態だ。
下記は人事院による人口千人当たりの公務員数の国際比較だが、これによると
フランス 89.5人
イギリス 69.2人
アメリカ 64.1人
ドイツ 59.7人
日本 36.7人
と圧倒的に少ない。しかも、地方公務員も入れた総数で見ればこの20年あまりで100万人以上減少していることになる (国家公務員に限っては半減!)。
この数字を見ただけでも、諸外国と比べて日本の公務員が激務に追われている実態は不思議でもなんでもない。むしろ当然の結果だろう。
※人事院HPより転載
https://www.jinji.go.jp/pamfu/profeel/03_kazu.pdf
公務員数の減少が与える影響
実際、この本のなかでもさまざまな実例を踏まえて「少人数で無理やり激務をこなしている官僚」の姿がありありと描かれている。
冒頭でも紹介したように
・65.6%は年間残業時間が720時間を超え、1000時間超えが42.3%、1500時間超えが14.8% (ちなみに過労死ラインは960時間と言われている)。
・朝7時に業務開始時間、仕事が終わるのが27時過ぎがザラ。
・本省で働く国家公務員に関して言えば、約一割が体調を崩して休職
という異常な状態が常態化するのも頷ける。
そして、実際このような異常事態は私達の生活にも影響を与えている。
たとえば昨今たびたび話題になる、コロナ禍による飲食店の時短営業への影響もその一つだ。
下記の朝日新聞の記事によれば
「新型コロナウイルスの感染急拡大を受け、1~3月に出された緊急事態宣言の対象11都府県で、営業時間短縮の要請に応じた飲食店などへの協力金の支給率にばらつきが生じている。福岡県が支給をほぼ終える一方で、大阪府は6割強にとどまることが朝日新聞の調査でわかった。(中略)
一方、申請が約11万4千件と2番目に多い大阪府は支給率が最も低い64%だった。期間別にみると、緊急事態宣言の最初の期限だった2月7日分までは78%で、11都府県の中で唯一90%台に達していない。2月8~28日分は49%にとどまる。民間企業に業務を一括委託したが、「判断に迷う事案が多く発生した」(府担当者)という。対応する府職員は3月末まで2、3人だけで支給は滞った。」
なぜこのような事態が起こるのかと言えば、店が実在するのか、時短要請の対象となるのか、営業許可証と確定申告の名前が一致しないなど、民間業者に判断できない事案が発生。それを大阪府職員に確認するものの、府側の担当者は2、3人しかいないために全く処理が追いつかない。
日本は公務員が多すぎるという思い込みにより減らし続けた結果、私たち国民自身が苦しんでいるのが実態だ。
もちろんこれは大阪府という一地方自治体の話だが、本書の官僚たちのブラック化も同根の問題を引き起こしているであろうことは想像にかたくない。
官僚と国民、双方にとってベストな方策を
著者は今回の新書を書いた理由を「まえがき」にて、次のように書いている。
「この本を書くことにしたのは、官僚を本当に国民のために働かせるためにはどうしたらよいか、それを皆さんと一緒に考えて実現していくためのきっかけとしたいからです。
(中略)
そして『そうだな。自分たちの税金で仕事をしている官僚には、国民のためになることに極力時間を使ってほしいな』。そう思ってくださったら、とても嬉しいです。」
長年官僚として働き、自身も身体を壊すほどに働いた人物の心からの訴えだ。
たしかに現在の官僚たちに何も問題がないわけではないだろう。上記の「人手不足」がその原因のすべてとも言えない。冒頭に述べた官僚の悪いイメージも、あながちすべてが幻想という訳でもないだろう。
だが、民間だろうが学校のサークルだろうが、どんな組織でも必ず制度的な問題を抱えているものだ。それを官僚システムにだけ「お前たちの努力が足りない。国民の税金で暮らしているのだから、滅私奉公を徹底しろ」と突き放すのは、やはり正当とは思えない。
官僚として働く彼らにも、彼らなりの言い分や、自分たちの力だけではどうしようもない課題もあるはずだ。
日本のはびこる、いわゆる「官僚」というイメージにとらわれることなく、官僚自身の声にも耳を傾けること。そして、国民と官僚お互いにとって少しでも良い環境を生み出せるように努力し合うことが大切ではないだろうか。
本書はそのための一助になるものとして、是非多くの人に一読して頂きたい。
というわけで今回ご紹介したのはこちら。
千正康裕「ブラック霞ヶ関」
でした。
今回も最後まで長文をお読み頂きありがとうございましたm(_ _)m
映画「るろうに剣心 The Beginning」。ファン歴30年が語る感想。

ついにこの時がやって来た・・・!
映画「るろうに剣心 最終章 The Beginning」が公開!
映画の初公開から足掛け10年にわたる歴史がついに終止符。
果たしてその結末とはいかに??
原作から数えて30年弱のファン歴を誇る一ファンの目にどのように映ったのかを語り尽くす。
※前作「The Final」については以前のこちらで投稿。
よろしければこちらも
- 総評
- The Beginningの素晴らしかった点
- 静かなアクション映画
- アクション性と物語性が融合した作品
- The Beginning単体の評価
- The Beginningのイマイチだった点
- それでも制作陣に感謝したい
総評
この映画「るろうに剣心」は、言わずもがな昔週刊少年ジャンプにて連載されていた漫画「るろうに剣心 明治剣客浪漫」を実写映画化した作品。
2012年に初作、2014年に京都大火編が公開。そして今年、原作の最終章「人誅編」に当たる「The Final」「The Beginning」が公開された。
実は原作では、このThe FinalとThe Beginningに当たる話は、ひと繋がりのストーリーとして描かれている(The Finalのパートは現在の話で、The Beginningのパートは主人公の”回想シーン”として描かれている)。
映画版では大胆にもこれを別作品として切り分けたのだが、”原作ファン”としてはちょっと考えられないアプローチであり、これが功を奏するのかが非常に気がかりとなっていた。
では、実際に映画版を観てどうだったのか?
結論から言えば・・・
めっちゃ面白かった!!(笑)
正直「これでつまらない作品になっていたら、原作レ○プとして、スタッフにクレーム入れてやろう。何なら原作者に”お前はこれで良かったと思っているのか”と投書してやろう。」と思っていたのだが(※冗談です)、そんな心配していたのがアホらしいくらいに面白かった!
ただし。
ただし、だ。
この作品だけを切り分けて一個の単独作品として見れば面白かったのだが、これをもって「るろうに剣心」という映画シリーズ全体が有終の美を飾ることができたのか?という意味では、手放しでは喜べないところがある。
各論としては素晴らしいが総論としては微妙だった、とでも言うべきか。この点についてもう少し詳しく考えてみよう。
The Beginningの素晴らしかった点
ストーリーとアクションのバランスが素晴らしい
何と言ってもストーリーとアクションのバランスが素晴らしい内容だった点を挙げるべきだろう。
今までのるろうに剣心は「時代劇アクション」と分類できる映画だった。主人公緋村剣心を演じる佐藤健の超人的な身体能力を最大限に引き出すべく、演出、シナリオ、カメラワークすべてが”息をつかせない”アクションシーンが最大の見せ場だった。いわゆるアメリカ映画的な派手さはないものの、その質においては世界にも誇れるレベルの高さだったと言えるだろう。
その一方でストーリーの深みという意味では、若干完成度に劣っていたところは否めない。賛否両論あるだろうが、あくまでアクションが主、ストーリーは従、という位置づけだったと言って差し支えないだろう。
しかし、今作においては緋村抜刀斎や雪代巴の心の動きを描くストーリーが中心で、アクションはそれを引き立てるための素材として上手く活用されていた。このバランスが絶妙だった。
今までの「アクション映画」を期待した観客には意外に映るかもしれないが、恐らく良い意味で期待を裏切る「るろうに剣心のドラマ性」を堪能できるのではないだろうか。
新しい「時代劇」の姿を見せた
次に素晴らしかったのは、「時代劇」という映画表現に新しいアプローチを見せたことだ。
映画るろうに剣心のプロデューサーである小岩井宏悦 (こいわい ひろよし) 氏によると、そもそも2009年に映画るろうに剣心のプロジェクトを立ち上げた際にも、「若い人は時代劇を観ない」という反対意見があったようだ。
当然だろう。
平成以降の世代で「時代劇を観るのが趣味」という人はほとんどいない。いくらイケメン俳優・佐藤健を主役にするからと言って、「時代劇でもこのコンテンツは成功する」と予想できなかっただろう。
だが、制作陣はその下馬評を見事に覆した。
佐藤健が若い世代を捕まえる取っ掛かりになったのは間違いないが、今までの日本映画にはなかった刀を使った息を呑むアクションで高い評価を勝ち取り、実績を残した (興行収入は初作が30億円、京都大火編が52億円、そして前作The Finalは5月末時点で既に興行収入30億円を突破)。
その意味ですでに映画るろうに剣心は既存の「時代劇」という枠を塗り替えたと言っても過言ではないが、今作The Beginningではそれをさらに超えるものを出してきた。
今まではスピード感や(刀のぶつかり合いなどの)サウンドを強調した”アクション映画として格好良い”というビジュアル重視の見せ方をとってきたが、今回は一転して”格好良い時代劇”を見せてきたのだ。その最大の違いは”静けさ”だ。
たしかにスピードやサウンドによる力強い映像は今までを踏襲している。しかし、今回の作品はとにかく”静か”なのだ。
静かなアクション映画
今回のThe Beginningが今までの作品と違うところの一つが「静けさ」にある。
もちろんそれは単純なボリュームの大小の話ではない。
大音量のシーンでもどこか寂しさを感じさせるような静けさを感じさせるのだ。
要因のひとつは、緋村抜刀斎が振るう刀の違いにある。
今までのシリーズでは主人公・緋村剣心が使っていたカタナは、刃と峰が逆になった”人を殺せない”刀、逆刃刀を振るっていた。そのためどうしても敵を倒すのに、何度も叩きつける必要がある。
しかし、今作の緋村抜刀斎が振るうのは普通の”人を殺せる刀”だ。つまり一振りで殺せる。結果、戦い自体は一瞬で決着がつく。
そのため多くの相手を斬り殺しても、戦闘シーン自体はそれほど長くならず、アクション映画的な大音量も少なくなっている。それによって物理的に静かという面がある。
そして、この作品の静けさのもう一つの要因は役者たちの演技にある。
作品を通じて感じたのは役者に無駄な動きがほとんどないことだ。分かりやすいのはヒロインである雪代巴(有村架純)の動きだろう。
巴が武家の人間という設定もあり、所作に無駄がなく、動きに大げさなところがない。役柄的に「クールビューティ」ということで、言葉や表情も非常に冷たい感じであるところが物語全般に静けさを与えている。
それ以外のキャラクターにしても、常に「いつ死ぬか分からない」という緊迫感があるせいか、無駄な動きがほとんどなく、結果的に今までの作品のような”賑やかな”空気感とは全く違う作品になっている。
アクション性と物語性が融合した作品
このアプローチは、るろうに剣心シリーズの派手なアクション性を期待した視聴者にとっては面食らうかもしれない。派手な剣戟アクションを求めたいた人からすれば、物足りない部分もあっただろう。
だが、見た目の派手さよりもキャラクターの心情、つまり緋村抜刀斎や雪代巴が抱える心の闇や心の変化の機微。そしてラストに向かって収束していく二人の悲劇的な運命をより深くえぐり出すのには、この静けさによる表現は非常に効果的だったと思う。
特に二人の最期のシーンにおいては、この静けさが二人の悲哀を極限にまで高めており、原作とは全く違う”はかなさ”と”美しさ”を描いていた。このシーンに関しては、もう完全に原作を超えたと言っても過言ではない。
この静けさこそが、日本映画でもトップクラスのアクション性と、これまでのるろうに剣心シリーズでは必ずしも突き詰められなかった物語性を、この作品において上手く融合させた要因ではないかと思う。
The Beginning単体の評価
という訳で。
るろうに剣心の原作からの熱烈なファンでもある私としては、The Beginningは予想を遥かに超えた素晴らしい作品だったと思う。
正直、雪代巴が有村架純だと聞いたときは「ないわ。マジないわ。有村架純に巴はできない。無理。」と思っていたのだが・・・・すみませんでした!!
私のイメージの巴とは違ったけれども、この作品の雪代巴としては確かに有村架純にしかできない役だったのかもしれない。
若干歴史的な知識や、原作を知らないと意味が分からないところがあるのは事実だが、るろうに剣心ファンではない人にもお勧めできる作品になっている。
The Beginningのイマイチだった点
・・・と、ここまではThe Beginningの良い点を挙げた。
しかし、この作品が100点満点だったのか?と言われれば、残念ながらそうは言えないのが事実だ。
確かにThe Beginning単体で観れば素晴らしい出来だったのは間違いない。
だが、るろうに剣心シリーズ全体の中での評価という意味では、「残念な結果だった」というのが正直なところだ。
ここからは完全に原作ファンとして見解となる。その点はご了承願いたい。
るろうに剣心のテーマとは何か
以前の投稿でも書いたのだが、私はこのるろうに剣心の映画化において「原作を忠実に再現すること」は求めていない。
重要なことは、るろうに剣心という作品が伝えたかったテーマを描けているかどうかだ。
るろうに剣心という漫画には非常に多くのテーマが込められているため、一つに絞ることは難しい。
だが、私の主観も込めつつ敢えて断言するなら
「人生の超克」と「魂の救済」
だと言えるだろう。
人生の超克とは、すなわち「辛く、苦しく、ときに悲しみに溢れた人生を生き抜くことの難しさ」を描くこと。
そして、人生を歩む中で誰しもが少なからず罪を背負うものだが、「その罪は愛する人や仲間の支えによって必ずや許される日が来る」という希望の道を描くこと。これが魂の救済である。
いささか大仰ではあるが、これこそが人斬りを主人公にしたるろうに剣心ならではのテーマだと思う。
しかし、残念ながらこれらのテーマは今作品では描かれなかったと言うしかない。
描かれなかった"人生の超克"
前作The Finalのレビューでも書いたことだが、今回のThe Beginningにあたる物語は、本来The Finalの中の回想シーンだ。
緋村剣心は自分の最愛の妻を惨殺したという罪を背負いながら、しかしその罪とは向き合えないままに10年間生きながらえてきた。
だが、10年の時を経てようやくその罪と向き合える心の強さと、信じられる仲間を持てるようになる。だからこそ、その罪を告白し、仲間や新たな伴侶とともにその罪を乗り越える覚悟をもつことができたという流れだ。
その意味でこのパートは単なる回想シーンではなく、緋村剣心が自分の罪と向き合う贖罪のシーンであり、その苦しみを共有することで仲間との絆をより一層深めるための試練でもあった (実際原作では回想シーンの後、仲間が一旦バラバラになるが、再びより絆を強くして集結するというストーリーになっている)。
つまり、The Beginningによって剣心の過去をえぐり出す過程があってこそ、The Finalが本来の意味を持つ。その過程がなければThe Finalの意味合いも半減する。
しかし、今回はこの二つを完全に切り分けるという手法を採用した。
上で書いた評価のように、これによりThe Beginning単体でのクオリティを上げることはできたのは事実だ。
だが、剣心が己の罪に向き合いそれを克服するとい過程はすっぽり抜け落ちてしまったのは否めない。
当然ながら、剣心は自分の人生を超克することができなかった。前作で敵役であった縁を倒したのは、あくまでその"人生の超克"の象徴だったはずなのだが、映画ではただの勘違いのシスコン男を力で倒し、相手に自分の過ちを認めさせて終了という、単なる勧善懲悪ドラマのような終わり方になってしまった。
誰の魂も救済されなかった
もう一つのテーマである魂の救済だが、これも残念ながら成し遂げられなかったと言える。人生の超克が成し遂げられてこその魂の救済なのだから当たり前だが…。
本来なら剣心が過去の罪に向き合い、心身ともにボロボロとなり、そこから立ち上がる過程において、周りからも赦され、自分自身を赦すプロセスが描かれるはずだった。
だが、剣心が自らの罪を乗り越える過程が描かれなかったため、このプロセスが描かれることもなかった(剣心も10年間苦しんで来たんだから、もう良いでしょ的な浅い扱い…)。
これは剣心の魂が救済されなかっただけではない。巴の魂もまた救済されなかったのだ。
巴が命をかけたのは、他でもない剣心を守るためだが、当然それは剣心が幸せに生きることを願ってのこと。結果的に巴の命を奪ったのは剣心だが、それに剣心が縛られ不幸になることは望んでいなかったはずだ。
したがって、剣心が巴の死に縛られたままでは、巴の魂も浮かばれない。剣心が救済されなければ、巴の救済されないまま。剣心が救済されて新たに幸せな人生を歩んでいく…それでこそ巴の魂もまた救済されるはずだった。
実際、原作では剣心と薫が巴の墓を見舞った際に、剣心が巴の墓に「ありがとう。済まない。そしてさようなら。」と告げ、薫立ち去るシーンがある。その際に巴の墓に穏やかな風が流れるのだが、それも正に剣心の幸せが巴の魂を救済したことを示す演出だったのだろう。
つまり、剣心の過去の回想をThe Beginningという作品に切り分けたことで、本来描かれなければならなかった"人生の超克"と"魂の救済"の物語がまったく描かれないという事態になってしまったのだ。
これは正直原作ファンとしてかなり残念だ。このような重いテーマを取り扱いながら、ちゃんと商業的にも成功した稀有な作品、それこそが「るろうに剣心」の魅力だった。それ以外の部分がとても優れた映画であった分だけ、肝心なテーマが削ぎ落とされたことは心残りだと言わざるを得ない。
それでも制作陣に感謝したい
ここまで辛辣なことを書いておきながら…ではあるものの、るろうに剣心という漫画史に残る名作を映画化してくれた制作陣やスタッフにはとても感謝している。
クオリティが予想を上回る出来だったため、「どうせならここまで描いて欲しかった」と述べたくなるものの、そもそもるろうに剣心の映画化自体が原作ファンにとっては夢のようなことだったのだ。
その夢を叶えてくれただけでも、とてつもなく有難いことだ。
その上、何度も書いているように、アクション性においては日本トップクラスなのは間違いない。それ以外の演出や映像の美しさ、迫力においてもずば抜けたクオリティの作品となっている。
漫画の映画化といえば"コレじゃない感"が漂う原作レイ◯の作品がお決まりだ。
だが、この映画るろうに剣心シリーズは、そのような心配を見事に裏切ってくれた。これほどの物を作り上げた関係者の努力には脱帽だ。本当に素晴らしい仕事をして頂いたと思う。
映画を観たことで改めて「るろうに剣心」という作品の素晴らしさについて考える機会が持てた。そして、さらに好きになることができた。このような貴重な機会を提供してくれた関係者の方々に心からお礼を述べたいと思う。





